「所有していた不動産を売却したけど、確定申告って必要なの?」
「何もしないと、後からペナルティがあると聞いて不安」
「不動産売却後の確定申告のやり方が分からないので、具体的な方法を知りたい」
不動産を売却した際、確定申告が必要か判断に迷う人は多くいます。売却利益が発生した場合は原則として確定申告が必要ですが、譲渡損失が生じたケースなど、不要なケースもあります。
しかし、判断を誤って申告を怠ると、無申告加算税などの重いペナルティが課される可能性があるため注意が必要です。
本記事では、確定申告が必要・不要かの判断基準や自分で申告する際の具体的なやり方、そして必要書類などを、初心者にも分かりやすく徹底解説します。本記事を読めば、税金で損をしないための正しい知識が身につき、安心して不動産の売却手続きを進められるようになります。
不動産売却後に確定申告は必要?不要?

不動産売却後の確定申告は、すべての人に必要というわけではありません。正しい判断をするためには、まず譲渡所得の計算方法を理解することが重要です。
不動産投資の確定申告はサラリーマンも必要!やり方や還付金のもらい方を解説
不動産売却後に確定申告が必要なケース
不動産売却によって利益が発生した場合は、原則として確定申告が必要です。具体的には以下のケースが該当します。
あなたの不動産今売るといくら?AI査定で無料で売却価格をチェック
譲渡所得が発生した場合
不動産の売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた結果、プラスの譲渡所得が生じた場合は確定申告が必要です。譲渡所得の計算式はこちらです。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
特例を利用するために確定申告が必要な場合
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」などの特例を受けるためには、譲渡所得税が発生しない場合でも確定申告が必要です。これらの特例は申告することで適用されるため、手続きを忘れると控除を受けられません。
不動産売却後に確定申告が不要なケース
一方で、確定申告が不要なのは以下のようなケースです。
譲渡所得金額がゼロかマイナスの場合
不動産を購入時より安い価格で売却し、譲渡損失が生じた場合は確定申告は不要です。ただし、損失を他の所得と損益通算したい場合は、任意で確定申告を行うことで翌年の税額を削減できる可能性があります。
譲渡所得と他の所得の合計が20万円以下の場合
給与所得者でひとつの会社に勤めており、年末調整をしている場合、譲渡所得とその他の所得の合計が20万円以下であれば確定申告は不要です。その他の所得には副業収入なども含まれるため、総合的に判断する必要があります。
ただし、譲渡所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。住民税の申告は確定申告とは別の手続きで、居住地の市区町村役場で行います。
不動産売却の確定申告が不要なケースの注意点
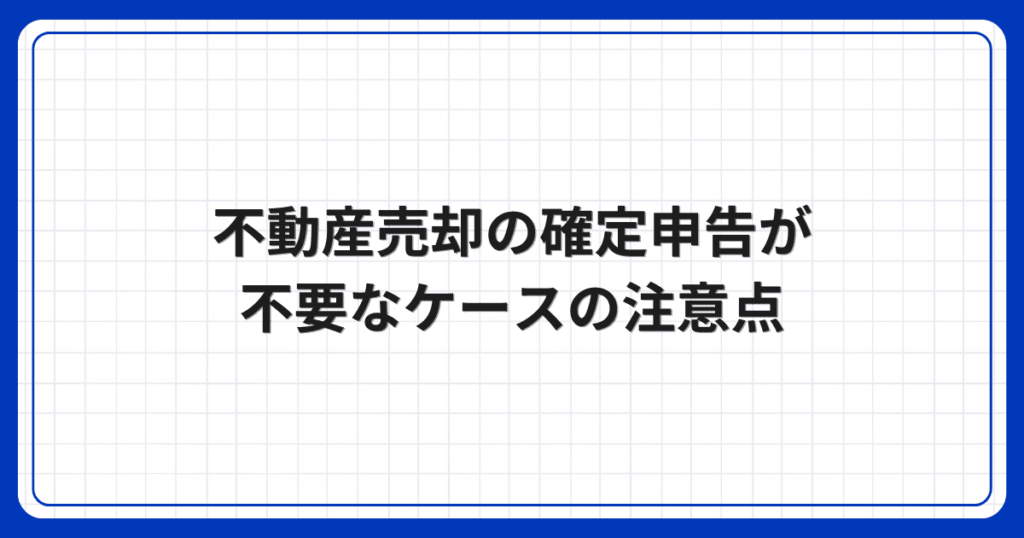
不動産売却で確定申告が不要と判断される場合でも、いくつかの注意点があります。判断を誤らないよう、慎重に検討する必要があります。
特例で控除を受けられることがある
マイホームを売却して損失が出た場合、確定申告すれば、損失分を給与所得や事業所得といった他の黒字の所得と損益通算できます(要件あり)。この仕組みにより、すでに源泉徴収などで納めた所得税が還付される可能性があります。
さらに、その年に控除しきれなかった損失は、翌年以降最大3年間にわたって繰り越して控除できる繰越控除という制度の利用が可能です。この特例の適用を受けるためには、損失が出ていても確定申告が必須です。
利益が出ても申告が不要になる特例がある
マイホームを売却して利益が出た場合でも、譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」があります。例えば、譲渡所得が2,500万円だったとしても、この特例を使えば課税対象額はゼロになり、所得税はかかりません。
ただし、このケースも特例の適用を受けるためには、確定申告を必ず行う必要があります。申告をしなければ特例は適用されず、多額の税金を納めることになりかねません。
不動産投資の失敗率は4割!5つの事例・体験談で学ぶ回避策と成功のコツ
不動産売却後の確定申告のやり方・手順
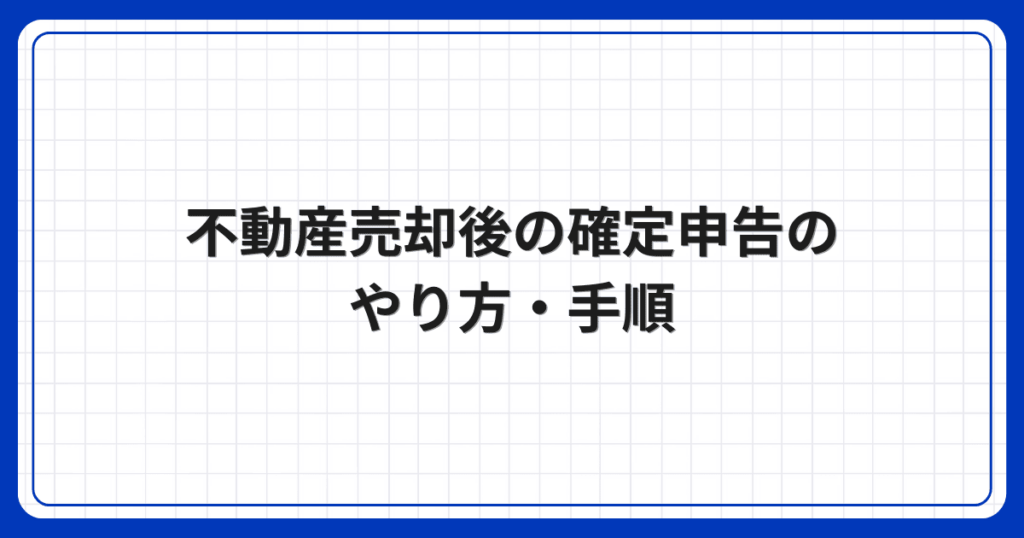
ここでは、確定申告が必要と判断された場合の具体的な手順を解説します。事前準備から提出まで、段階的に進めることで確実に手続きを完了できます。
STEP1:必要書類を揃える
まずは、確定申告に必要な書類を事前に準備します。必要書類の詳細については、次の「不動産売却の確定申告の必要書類」で詳しく解説しているため、そちらを参考に準備を進めてください。
STEP2:譲渡所得を計算する
売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて譲渡所得を算出します。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算することも可能です。
STEP3:確定申告書を作成する
計算した金額をもとに、確定申告書を作成します。作成方法は、税務署で用紙をもらって手書きする方法のほか、国税庁のWebサイトにある確定申告書等作成コーナーを利用するのが便利です。
画面の案内に従って入力するだけで、自動的に税額が計算されます。e-Taxを利用すれば、スマホからでも申告書の作成・提出が可能です。
STEP4:確定申告書を提出する
作成した確定申告書を税務署に提出します。申告期間は、不動産を売却した年の翌年2月16日〜3月15日です。
提出方法は税務署への持参、郵送、e-Taxによる電子申告の3種類です。e-Taxなら24時間いつでも提出でき、添付書類の提出も省略できる場合があります。
不動産売却の確定申告の必要書類
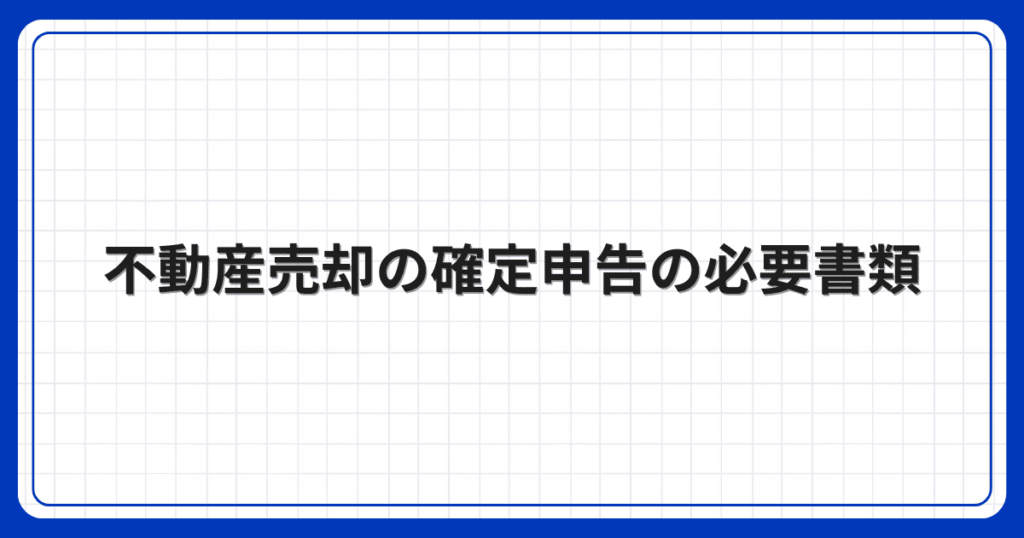
不動産売却の確定申告でもっとも手間がかかるのが、必要書類の収集です。直前になって慌てないよう、下記のリストを参考に計画的に準備を進めましょう。
| 必要書類 | 内容 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 確定申告書(第一表・第二表) | 所得税の確定申告に使用する基本書類 | 税務署または国税庁Webサイトから入手する |
| 確定申告書(第三表・譲渡所得の内訳書) | 譲渡所得の詳細を記載する書類 | 税務署または国税庁Webサイトから入手する |
| 不動産売買契約書 | 物件の売買契約を締結した書類 | 不動産会社から受け取る |
| 仲介手数料などの領収書 | 譲渡費用を証明する書類 | 不動産会社や関係業者から受け取る |
| 登記事項証明書 | 不動産の詳細情報を記載した公的書類 | 法務局で取得する |
| 固定資産税精算書 | 固定資産税の精算内容を記載した書類 | 売買時に不動産会社から受け取る |
不動産売却後の確定申告は税理士に依頼すべき?
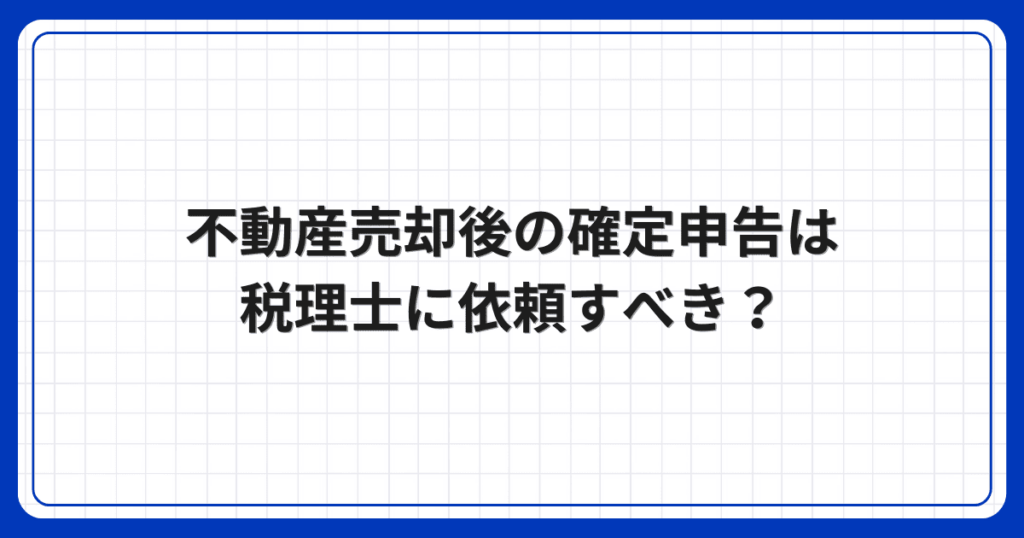
不動産売却の確定申告は個人でも可能ですが、自分でやる自信がない人は税理士に依頼することをおすすめします。
不動産投資は税理士に相談すべき?費用の相場やメリット、選び方などを解説
税理士に依頼すれば、書類の準備から申告書の作成・提出まですべて代行してくれるため手間が省け、計算ミスや申告漏れのリスクがなくなる点が大きなメリットです。また、依頼者にとってもっとも有利な特例の適用や経費計上を提案してくれるので、結果的に自分で申告するより納税額を抑えられる可能性もあります。
税理士費用の相場は、確定申告の代行を依頼する場合、5万円〜15万円程度が一般的です。売却金額や複雑さによって費用は変動しますが、節税効果や申告ミスによるリスクを考慮すると、費用に見合う価値がある場合が多いでしょう。
一方で、比較的シンプルなケースであれば、自分で申告することも可能です。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の指示に従って入力するだけで申告書を作成できます。
税理士費用を節約したい場合は、まず自分で挑戦してみて、分からない部分があれば税務署の相談窓口を利用する方法もあります。
不動産売却の確定申告で経費として計上できる費用
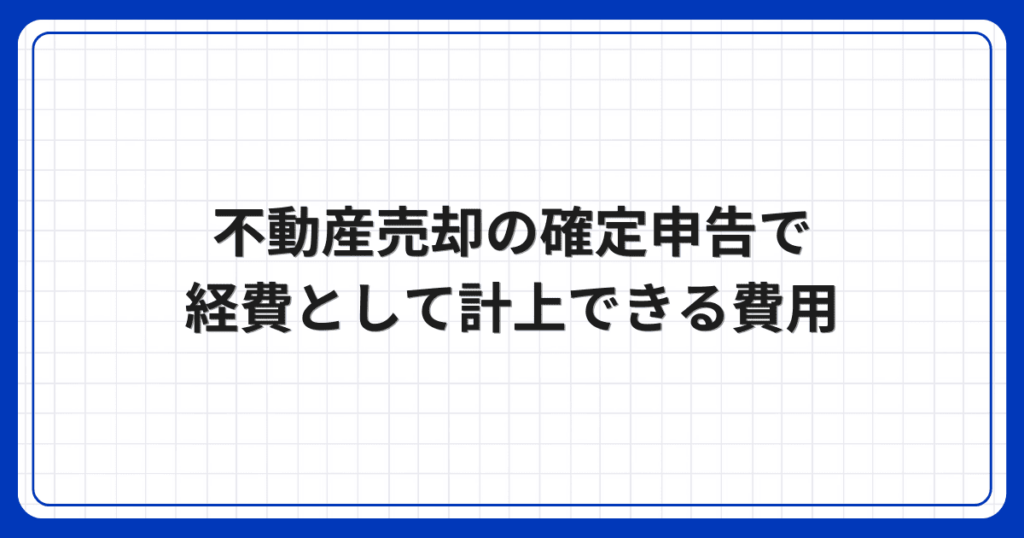
不動産売却時の経費を適切に計上することで、譲渡所得を減らし、節税効果を得られます。どのような費用が経費として認められるのかを理解しておきましょう。
あなたの不動産今売るといくら?AI査定で無料で売却価格をチェック
経費計上で節税になる仕組み
譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で計算されます。譲渡費用が多いほど譲渡所得は少なくなり、結果として税額も減少します。適切に経費を計上することで、合法的な節税が可能です。
不動産売却の経費として計上できる費用
不動産売却に直接かかった費用は譲渡費用として計上できます。代表的な例はこちらです。
- 物件売却時の仲介手数料
- 印紙税
- 解体費用
- 改修費用(売却のため)
- 広告費用
- 清掃費用
これらの費用は売却のために直接的に支出したものであり、領収書等で金額を証明できることが条件です。
また、不動産の取得時にかかった費用も取得費として計上可能です。
- 物件の購入代金
- 物件購入時の仲介手数料
- 登記費用
- 不動産取得税
- 測量費用
不動産売却の経費として計上できない費用
一方で、売却に直接関係しない費用は経費として認められません。不動産売却の経費として計上できない費用の一例はこちらです。
- 固定資産税や都市計画税などの保有期間中の税金
- 管理費や修繕積立金
- 住宅ローンの利息
- 仮住まい費用
ただし、これらの費用の中でも売却を目的として支出したものであれば、譲渡費用として認められる場合があります。判断が困難な場合は、税務署に相談するか税理士に確認することをおすすめします。
不動産売却の確定申告をしないとどうなる?
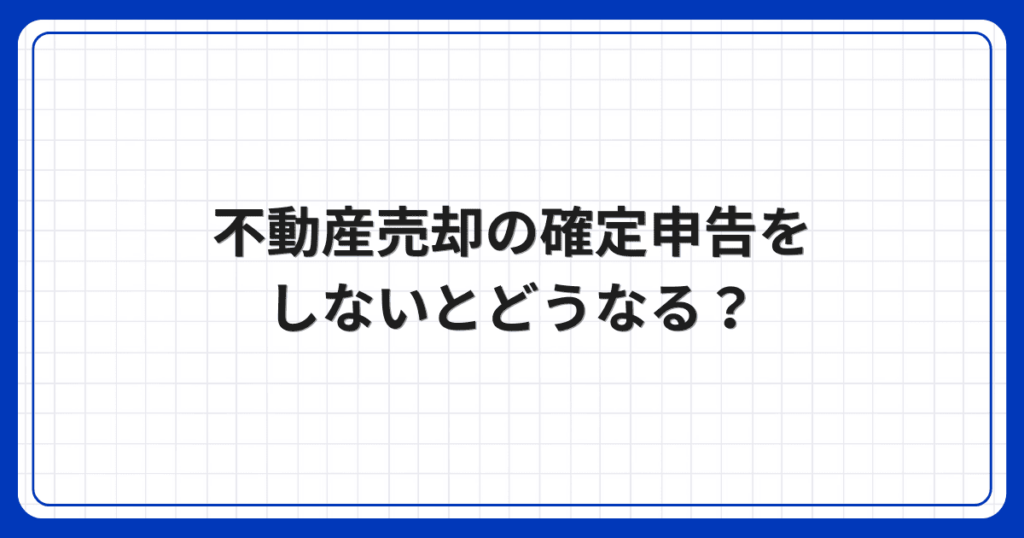
不動産売却で譲渡所得が発生しているにもかかわらず確定申告を怠った場合、税務署からペナルティが課される可能性があります。
| 種類 | 原因 | 負担額 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 申告期限までに確定申告をしなかった | 50万円までの部分は15% 50万円を超え300万円までの部分は20% 300万円を超える部分は30% |
| 過少申告加算税 | 申告額が本来より少なかった | 原則10%} 不足税額が50万円超部分は15% |
| 重加算税 | 意図的に所得を隠蔽・仮装した | 追加で納める税額の35%〜40% |
| 延滞税 | 納税が期限より遅れた | 納付期限から2か月以内は年2.4% 2か月超は年8.7% |
これらのペナルティにより、本来納めるべきだった税額より、はるかに重い負担を強いられることになります。確定申告は必ず期限内に正しく行いましょう。また、税率は年によって変動するため、最新の情報は国税庁のWebサイトを確認してください
不動産売却の確定申告に関するよくある質問
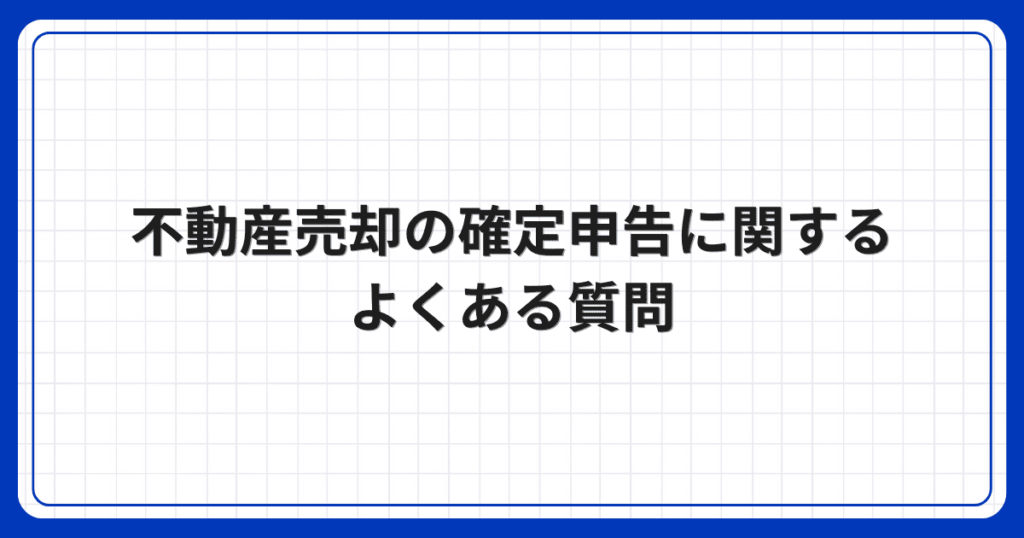
不動産売却の確定申告に関するよくある質問について回答します。
- 相続した不動産を売却した場合にも確定申告は必要?
-
相続によって取得した不動産を売却した場合も、譲渡所得が発生すれば確定申告が必要です。相続の場合の取得費は、被相続人が購入した時の金額を引き継ぎます。
また、相続にあたって相続税を支払っている場合は、税金の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」が使える可能性があるため、確認しましょう。
- 共有名義の不動産を売却した場合の確定申告はどうなる?
-
共有名義の不動産を売却した場合、共有者一人ひとりが自分の持分割合に応じた譲渡所得を計算し、各自で確定申告を行う必要があります。例えば売却益が1,000万円で、持分が兄弟で2分の1ずつだった場合、それぞれが500万円の譲渡所得として申告します。
ただ、共有名義の不動産売却は複雑な計算が必要で、個人で対応するのは難しいでしょう。自分で確定申告するのに不安を覚えた時は、専門家への相談を検討することをおすすめします。
不動産売却の確定申告が不安ならプロパリー
引用元:プロパリー
| 価格 | 無料 |
| 対応OS | iOS/Android |
| 4つの強み | プロを比較して選べる 将来の収支予測 リアルタイム収支管理 買主から直で売却オファー |
確定申告の複雑さもさることながら、不動産売却で損をしないためには、できるだけ早い段階で頼りになるパートナーを見つけることが重要です。しかし、自分に合うパートナーを選ぶのは、初心者にとって容易ではありません。
そんな悩みを解決するのが、中立的な第三者の立場で、売却希望者に最適な不動産投資のプロを紹介してくれるマッチングサービス「プロパリー」です。
プロパリーの最大の強みは、その徹底した中立性にあります。プロパリー自身は不動産の売買を行わないため、特定の不動産会社に有利な売却活動を行うことはありません。
売却希望者が物件情報を登録すると、その物件を売りたいと考える実績豊富な複数の専門家から、具体的な査定額や売却戦略の提案が届きます。売却希望者は、それらの提案をじっくり比較検討し、もっとも信頼できると感じたパートナーを選ぶだけです。
プロパリーを活用することで、不動産の資産価値を最大化してくれる、最適なパートナーを客観的な視点で見つけられます。また、不動産売却における確定申告が不安な人にも、必要に応じて税理士の紹介も可能です。
プロパリーは無料で利用できます。不動産売却で後悔しないためにも、まずはプロパリーをダウンロードして、頼りになるプロを見つけましょう。
まとめ:不動産売却の確定申告は正しく行おう
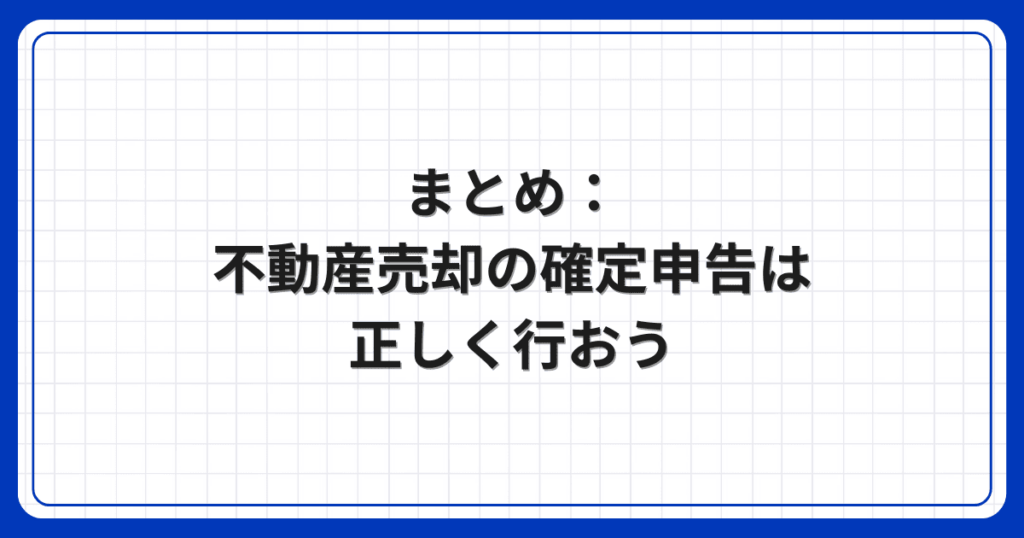
不動産売却後の確定申告は、譲渡所得の発生状況や適用される特例によって要否が決まります。確定申告を怠ると、無申告加算税などの重いペナルティが課される可能性があるため、不動産売却後は必ず申告の要否を確認しましょう。
また、確定申告が不要な場合でも、損益通算や繰越控除により翌年以降の税負担を軽減できる可能性があるため、税務の専門家に相談することをおすすめします。もし、自分で相談するパートナーを選べないのであれば、プロパリーがおすすめです。
プロパリーは公平な立場から、利用者に寄り添った信頼性の高い不動産投資のプロを紹介してくれます。確定申告の悩みはもちろん、不動産売却に関しても相談に乗ってくれるので、安心して手続きを進められます。
この機会にプロパリーを活用し、不動産売却の確定申告を正しく行いましょう。














