「不動産投資は節税になると聞いたことがあるけど、本当なの?」
「不動産投資で節税効果の高い物件を知りたい」
サラリーマンとして働いていると、所得税や住民税が高いと感じることがあるでしょう。税金対策として、不動産投資の節税効果に興味を持っている方は多くいます。節税を目的とした不動産投資は有効なのでしょうか?
確かに不動産投資によって、所得税と住民税の節税が可能です。正しく行えば、ふるさと納税やiDeCo以上の節税効果を得られることもあります。
しかし、不動産投資の節税の仕組みや注意点などを知らなければ、税金を抑えるどころか、投資としても大きな損失を抱えかねません。
本記事では、不動産投資の節税の仕組みや注意点、節税シミュレーションについて解説していきます。本記事を読めば、節税効果の高い物件を選べるようになり、より多くの資金を手元に残せるようになります。
また適切に節税を行うためには、不動産投資の収支を正しく管理することが欠かせません。その大前提がまだできていない方は、不動産オーナー向けのおすすめアプリ4選から自分に合うアプリを見つけ、導入することをオススメします。

不動産投資するならプロパリー・資産管理・物件シミュレーション
誰でも完全無料で、不動産投資の基本から実際の購入・運用まで詳しく学べる学習アプリです。
プロパリーは不動産会社ではないからこそ、物件を売りたいだけの業者には伝えられない、真実の情報を提供しています。
不動産投資は所得税や住民税の節税になる!
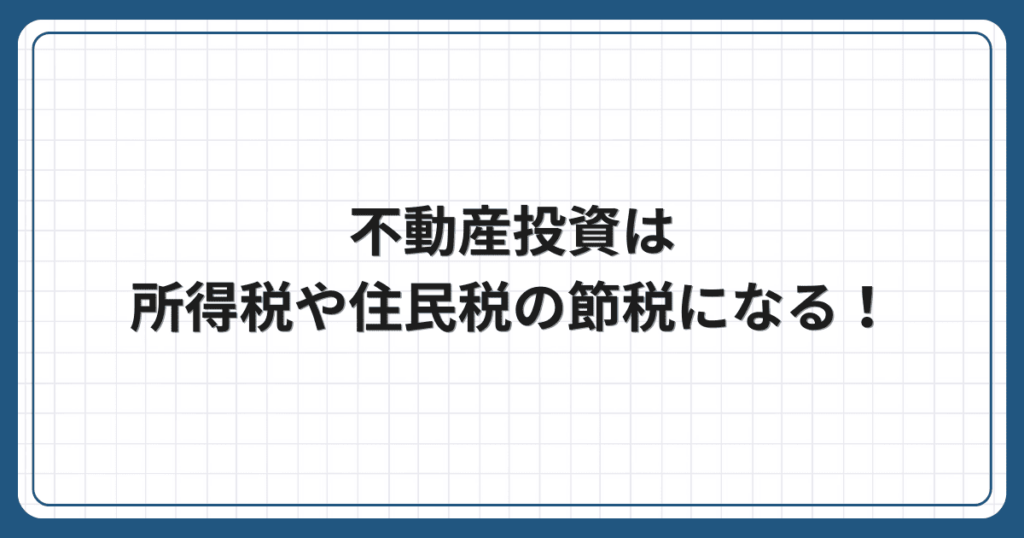
不動産投資をすると、所得税と住民税の節税が可能です。まずは、不動産投資で節税できる税金の種類について把握しておきましょう。
不動産投資の節税は主に2種類
不動産投資の節税には、下記の2種類があります。
- 税金を減らす方法
- 税金を繰り延べる方法
サラリーマンが節税する方法は1です。減価償却と損益通算を利用して、所得税と住民税の支払いを軽減できます。減価償却と損益通算については後ほど解説します。
法人が節税する方法は2です。減価償却を利用して課税を繰り延べしておき、赤字の年に物件を売却して赤字分と売却益を相殺します。
不動産投資で節税できる税金の種類
不動産投資で節税できる税金の種類には、下記の4種類があります。
- 所得税
- 住民税
- 贈与税
- 相続税
所得税
「所得税」とは、収入から経費を差し引いた所得に課される税金のことです。所得が高くなるにつれて課税される金額も高くなる「累進課税制度」が採用されています。
| 所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円~ | 45% | 4,796,000円 |
所得金額に税率を掛け、控除額を引いた金額に課税されます。
住民税
「住民税」とは、在住している地方自治体に納める税金のことです。住民税は所得金額に関わらず納める金額が決まっている「均等割」と、所得金額に応じて課税額が変動する「所得割」から構成されています。
贈与税
「贈与税」とは、他者から財産を譲り受けた際に課税される税金のことです。贈与税には110万円の控除が適用されます。譲り受けた財産が110万円以下であれば、贈与税を支払う必要はありません。
相続税
「相続税」とは、故人から財産を相続するとき、相続人に課される税金のことです。相続した財産が大きければ大きいほど、相続税額も大きくなります。不動産は現金や有価証券とは異なり、相続税評価額が現金価値よりも低くなる傾向があるため、相続税対策としても活用されることがあります。
不動産投資で節税できる仕組み
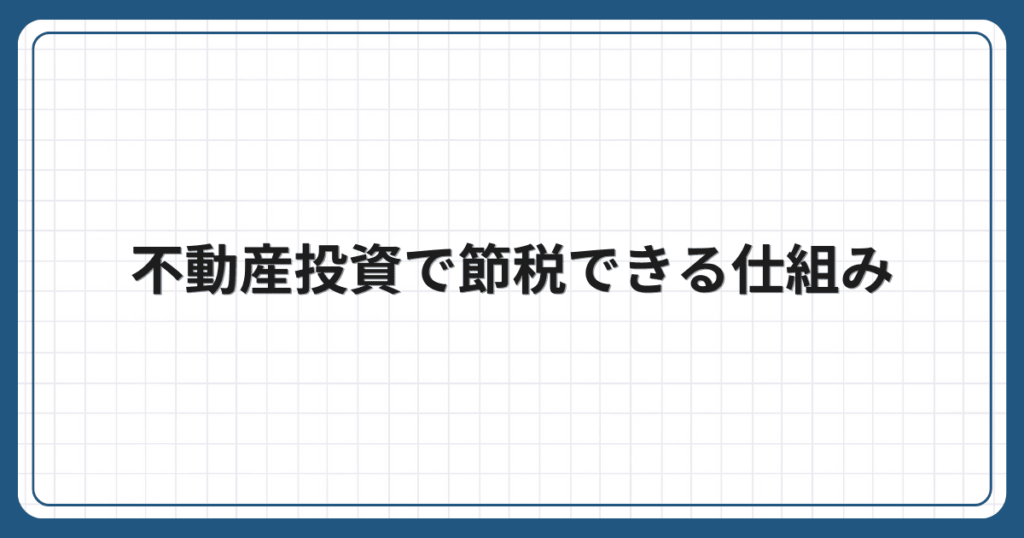
不動産投資はなぜ節税ができるのでしょうか。ここからは、不動産投資で節税できる仕組みについて解説していきます。
このほか具体的な節税のコツやメリット・デメリットなどを一通り効率良く知りたいなら、学習アプリ「プロパリー」がオススメです。プロパリーは不動産会社ではないからこそ、物件販売ノルマもなく、不動産投資について偏りのない情報を発信しています。
しかもすべてのコンテンツ・機能が無料で利用可能です。不動産投資をやるべきか迷っているなら、まずはプロパリーをやってから判断しましょう。

不動産投資するならプロパリー・資産管理・物件シミュレーション
誰でも完全無料で、不動産投資の基本から実際の購入・運用まで詳しく学べる学習アプリです。
プロパリーは不動産会社ではないからこそ、物件を売りたいだけの業者には伝えられない、真実の情報を提供しています。
減価償却が使える
「減価償却」とは、資産が使用できる期間に応じて分割して費用計上する方法です。これは、時間の経過とともに減少すると考えられる建物などの資産価値を、会計上反映させるための処理です。
例えば、3,500万円のワンルームマンションを購入するとします。減価償却期間が10年の場合、毎年350万円ずつを費用計上できます。
費用計上により利益を減らせるため、納税額をおさえることが可能です。なお、減価償却が使えるのは建物部分のみで、土地には使えません。
赤字を損益通算できる
「損益通算」とは、所得の黒字と赤字を相殺することです。サラリーマンが不動産投資をすると、給与所得と不動産投資の赤字分の相殺が可能です。
例えば、本業の所得が700万円のサラリーマンが、不動産投資で400万円の赤字を出したと仮定します。この場合、本業所得の700万円から赤字分の400万円を差し引くことができるため、相殺後の金額である300万円に所得税と住民税がかかります。
不動産投資で赤字を出したときは、必ず確定申告を行い損益通算しましょう。
なお、土地の借り入れの利子などは、損益通算の対象外です。赤字となった原因によっては、損益通算ができない点に注意してください。
かかった費用を必要経費として計上できる
不動産の購入時や運用時にかかった費用は、必要経費として計上できます。必要経費の一例はこちらです。
- ローンの金利(金融機関からの融資にかかる金利)
- 固定資産税や不動産取得税などの税金
- 仲介手数料
- 管理委託料
- 修繕費
なお、不動産投資に関係のない食事代や交際費、事業者の給与などは不動産投資の経費として計上できません。
不動産投資の節税効果を年収別にシミュレーション
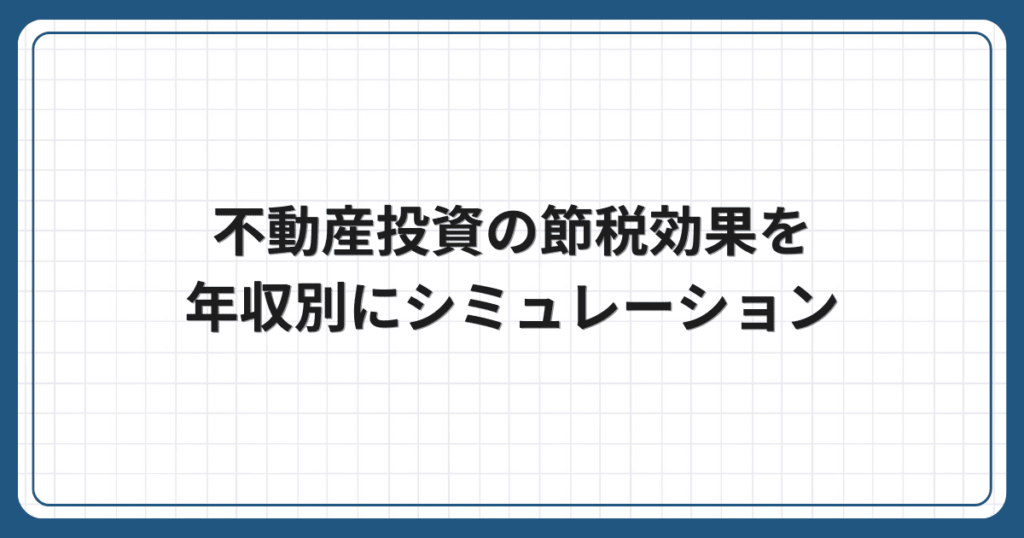
では、具体的例をもとにシミュレーションしていきましょう。
不動産投資の節税効果はどれくらいあるのか、シミュレーションしてみました。シミュレーション方法が分かれば、自分の年収にあてはめて計算できるようになります。
節税効果のシミュレーション方法
不動産投資の節税効果をシミュレーションする際は、給与収入と家賃収入、諸経費などを把握しておく必要があります。では、具体例をもとにシミュレーションしていきましょう。
本記事では、年収800万円で不動産投資をしていない人と不動産投資をしている人の2パターンを紹介します。不動産所得をしている人は、100万円の赤字が出ている状態とします。
課税所得450万円から100万円の赤字を差し引くことができるので、不動産投資をしている場合の所得税と住民税は以下のとおりです。
| 不動産投資をしている | 不動産投資をしていない | |
|---|---|---|
| 課税所得 | 3,500,000円 | 4,500,000円 |
| 所得税 | 272,500円 | 472,500円 |
| 住民税 | 355,000円 | 455,000円 |
| 納税額 | 627,500円 | 927,500円 |
今回のケースでは、不動産投資をすることで30万円もの節税に成功しました。
節税効果が出る年収の目安は1,300万円
年収1,3000万円の人の所得は919万円です。所得が900万円を超えると所得税率が33%になります。高い税率が適用されるため、減価償却費や諸経費を計上して課税所得を低くできれば、節税効果が期待できます。
日本のサラリーマンのおよそ4分の1は、600万円以上の年収があります。しかし、年収600万円のサラリーマンの所得は466万円なので、大きな節税効果は期待できません。
高年収の人ほど高い節約効果が期待できます。
不動産投資による節税効果が高い物件の選び方
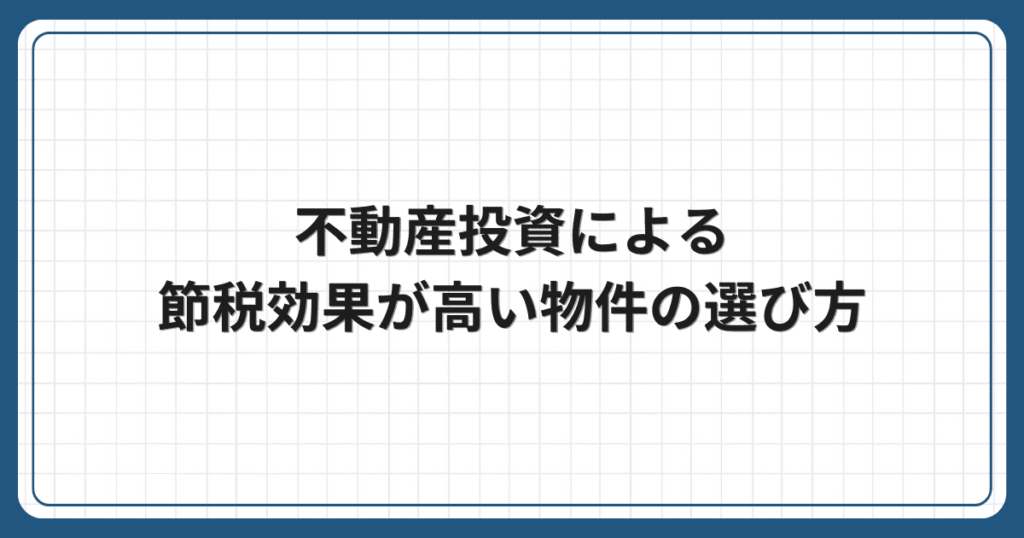
不動産投資の節税効果を発揮するためには、物件選びも重要です。節税効果の高い物件を選ぶことで、税金の支払いをおさえることが可能です。
ここからは、不動産投資による節税効果の高い物件の選び方について解説していきます。
節税の効果が出やすいのは築古の木造物件
木造物件は鉄筋コンクリート造などの構造よりも、耐用年数が短い特徴があります。そのため、減価償却費を多く計上できる点がメリットです。
構造別の耐用年数は、こちらの表を参考にしてください。
| 建物の構造 | 耐用年数 |
|---|---|
| 木造 | 22年 |
| 軽量鉄骨造 | 27年 |
| 重量鉄骨造 | 34年 |
| 鉄筋コンクリート造 | 47年 |
また、築古物件は減価償却期間が短くなります。一般的に中古物件は新築に比べて取得価格が抑えられる傾向にある点も、初期投資の観点からメリットとなる場合があります。よって、節税効果を高めるためには、築古の木造物件が最適だと判断できます。
節税の効果が出にくいのは新築の区分マンション
一方で、不動産投資の節税効果を期待している場合、新築の区分マンションへの投資はおすすめできません。
区分マンションの構造は、鉄筋コンクリート造や重量鉄骨造であるケースがほとんどです。鉄筋コンクリート造や重量鉄骨造の耐用年数は長いため、1年あたりの減価償却費が低くなります。
ただ新築区分マンションは節税効果を得られにくいとはいえ、設備が新しいため入居者が見つかりやすい、築浅の段階であれば売却しやすいなどのメリットもあります。
【この記事を読んだ人にはこちらもオススメ】



不動産投資で節税を狙う際のコツ・注意点
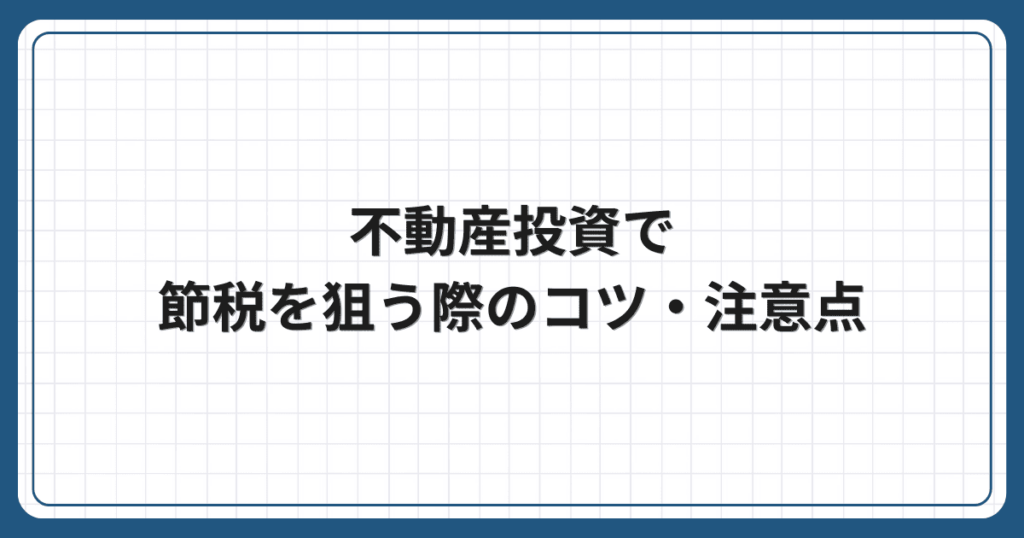
不動産投資で節税を狙う際は、コツや注意点について把握しておきましょう。コツや注意点について把握しておかなければ、十分な節税効果が出ない可能性が高まります。
不動産投資のリスクを理解する
不動産投資には、空室リスクや家賃下落リスクなどがあります。例えば空室リスクの対処を怠った結果、空室が発生して賃料収入を得られなければ、節税できる金額以上の損失となってしまい、節税効果が薄れてしまいます。
節税効果のみに着目せず、家賃下落リスクや運営コストなどの不動産投資のリスクについて理解したうえで、賃貸経営を行うようにしましょう。物件の収益性もしっかりと評価し、総合的に判断することが重要です。
キャッシュフローを適切に管理する
「キャッシュフロー」とは、家賃収入から諸経費を引いたお金の流れのことです。これは不動産投資における実質的な収益を示します。
不動産投資では、予期せぬ事態が発生することがあります。キャッシュフローを適切に管理することで資金繰りの安定化につながり、突発的な出費に備えられます。
デッドクロスの発生に気をつける
不動産投資におけるデッドクロスとは、ローン元金返済額(借入金の元金返済額)が減価償却費を上回る状態を指します。デッドクロスが発生するとローン返済が難しくなり、帳簿上では黒字状態でも現金が不足する黒字倒産となる可能性があります。
物件購入時に自己資金を多めに入れておくことで、デッドクロスの防止が可能です。また、減価償却期間の長い物件を購入することも有効です。
確定申告を正しく行う
不動産所得が年間20万円以上あるサラリーマンは、確定申告を行う必要があります。また、不動産投資を始めたばかりのサラリーマンは赤字となるケースが多いですが、確定申告により税金の還付を受けられる場合もあります。
さらに確定申告をすることで、損益通算や繰越控除の活用が可能です。確定申告には白色申告と青色申告があり、一定の要件を満たして青色申告を行うと、特別控除が適用されるなど、さらなる節税メリットがあります。確定申告を正しく行い、節税につなげてください。申告内容が複雑な場合や、判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
不動産投資の確定申告については、こちらの記事で詳しく解説しています。

節税の仕組みや物件選びのコツなど効率良く学ぶならプロパリー
引用元:プロパリー
| 価格 | 無料 |
| 対応OS | iOS/Android |
| 4つの強み | プロを比較して選べる 将来の収支予測 リアルタイム収支管理 買主から直で売却オファー |
不動産投資には節税効果の他にも、多くのメリットがあります。一方で投資である以上、デメリットがあるのも事実です。リスクを避け、不動産投資のメリットを最大に活かすためには、正しい知識が欠かせません。
そこでオススメなのが、学習アプリ「プロパリー」です。プロパリーは不動産会社ではないからこそ、不動産投資に対して中立な立場で情報を発信しています。
提供するのは、不動産会社にとって都合の良い話ではなく、投資家にとって有益な情報です。だからこそプロパリーを使えば、物件選びや業者選びで間違えるリスクを大きく減らせます。
しかもプロパリーは、すべてのコンテンツを無料で利用可能です。不動産投資の勉強をプロパリー1つで済ませれば、大切なお金と時間を実際の投資に注ぎ込めるので、今すぐインストールしてください。

不動産投資するならプロパリー・資産管理・物件シミュレーション
誰でも完全無料で、不動産投資の基本から実際の購入・運用まで詳しく学べる学習アプリです。
プロパリーは不動産会社ではないからこそ、物件を売りたいだけの業者には伝えられない、真実の情報を提供しています。
不動産投資の節税に関するよくある質問
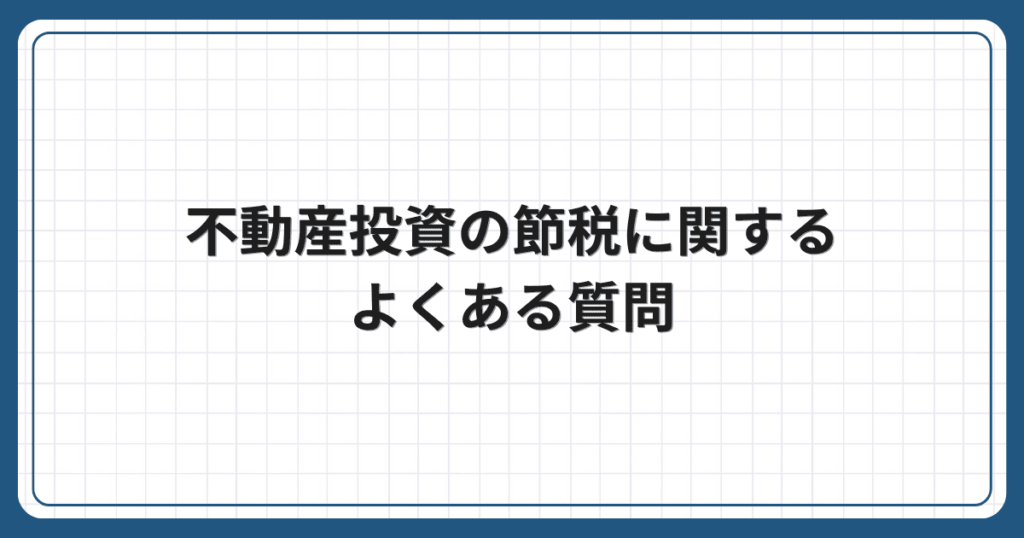
不動産投資の節税に関するよくある質問について回答していきます。
- 減価償却期間が復活することはある?
-
物件の所有者が変わると、減価償却期間が復活します。現所有者から次の所有者に変わる場合、物件の取得時点から減価償却期間を計算します。
耐用年数が経過した物件の減価償却期間の計算方法はこちらです。
耐用年数×20%
耐用年数の一部が経過した物件の減価償却期間の計算方法は、下記の通りです。
(耐用年数-築年数)+築年数×20%
ただし、家族間売買などを行った場合、減価償却期間の復活が認められないケースもあります。
- 不動産投資が赤字でも節税効果はある?
-
不動産投資が赤字でも節税効果はあります。
損益通算を活用すれば、不動産投資の赤字分を給与所得などのほかの所得と相殺可能です。相殺後の所得金額に対して課税されるため、住民税と所得税を節税できます。
不動産投資で赤字が出たサラリーマンは、忘れずに確定申告をしましょう。
- 法人化したほうが所得税を節税できる?
-
法人化により所得税の節税につながるかどうかは条件によります。下記の条件に該当している人は、法人化による所得税の節税が期待できます。
- 事業規模で不動産投資をしたい人
- 所得税の税率が20%を超える人
まとめ:不動産投資で賢く節税して資産を増やそう
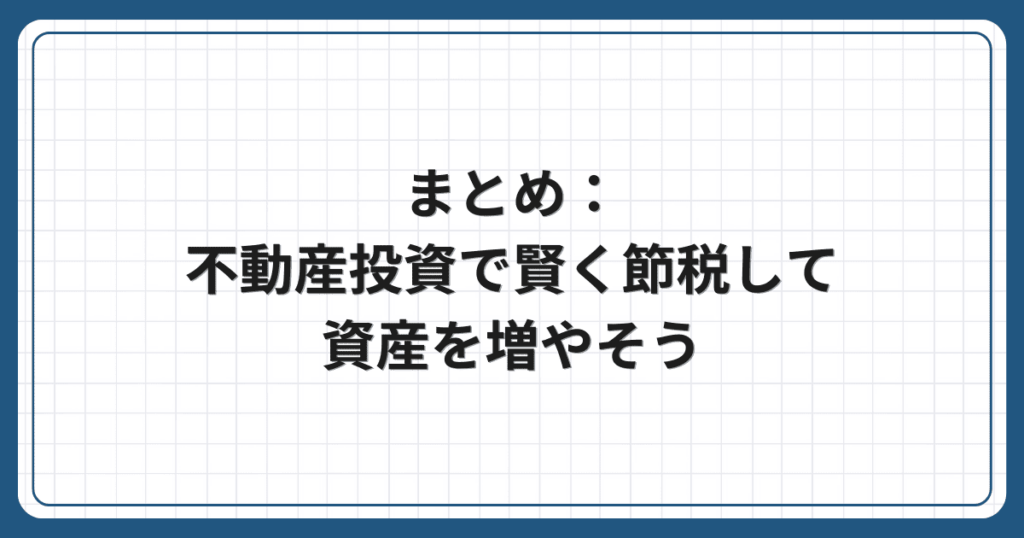
不動産投資をすることで、所得税や住民税の節税になります。これは資産形成を進める上での一つの手段となり得ます。減価償却や損益通算、必要経費の計上により、節税ができます。
節税効果が出る年収の目安は1,300万円です。しかし、損益通算を活用することで、年収が1,300万円未満の人でも十分な節税効果を狙えます。
ただし損益通算や確定申告によって、節税効果を正しく発揮させるためには、不動産投資の基本を理解しておかなければなりません。忙しい人でも基本を効率良く学べるのが、不動産投資の学習アプリ「プロパリー」です。
不動産販売業者ではないからこそ、不動産投資のメリット・デメリットを公平に伝え、成功へ導きます。無料で簡単に始められるので、「不動産投資の最初の一歩を間違えたくない」「失敗したくない」という方は、今すぐインストールしてください。

不動産投資するならプロパリー・資産管理・物件シミュレーション
誰でも完全無料で、不動産投資の基本から実際の購入・運用まで詳しく学べる学習アプリです。
プロパリーは不動産会社ではないからこそ、物件を売りたいだけの業者には伝えられない、真実の情報を提供しています。













