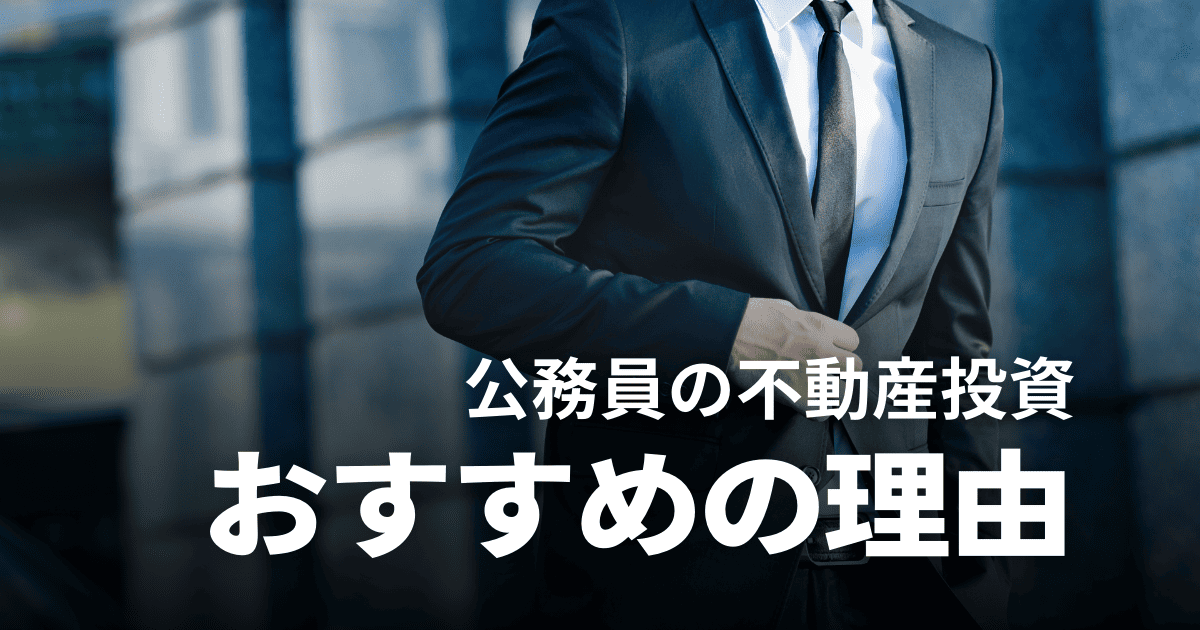「公務員は副業禁止といわれているけど不動産投資もダメなの?」
「公務員の不動産投資が認められる条件を知りたい」
「公務員が不動産投資で成功するコツや体験談を知りたい」
公務員は営利目的の副業が原則禁止とされており、不動産投資に興味はあるものの諦めている人も多いでしょう。しかし、一定の条件を満たすことで、公務員も不動産投資が可能です。
本記事では、公務員の不動産投資が認められる条件や成功のコツ、体験談などを解説しました。本記事を読むことで、規則に抵触することなく不動産投資を始められるようになり、安定した家賃収入を得られる可能性を高められます。
公務員の不動産投資は副業禁止に該当する?
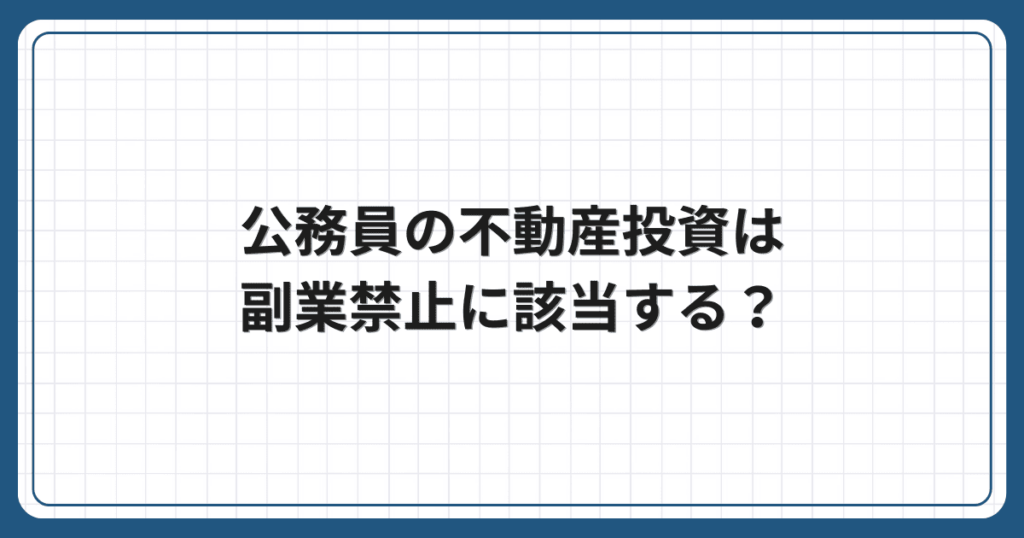
公務員は国家公務員法第103条および第104条、地方公務員法第38条により、原則として営利目的の副業が禁止されています。
国家公務員法第103条
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
e-GOV
国家公務員法第104条
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
e-GOV
地方公務員法第38条
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
e-GOV
しかし、不動産投資については一定の条件を満たす場合に限り、副業とみなされずに行うことが可能です。ルールを正しく理解することが何よりも大切です。
公務員の不動産投資が認められる条件
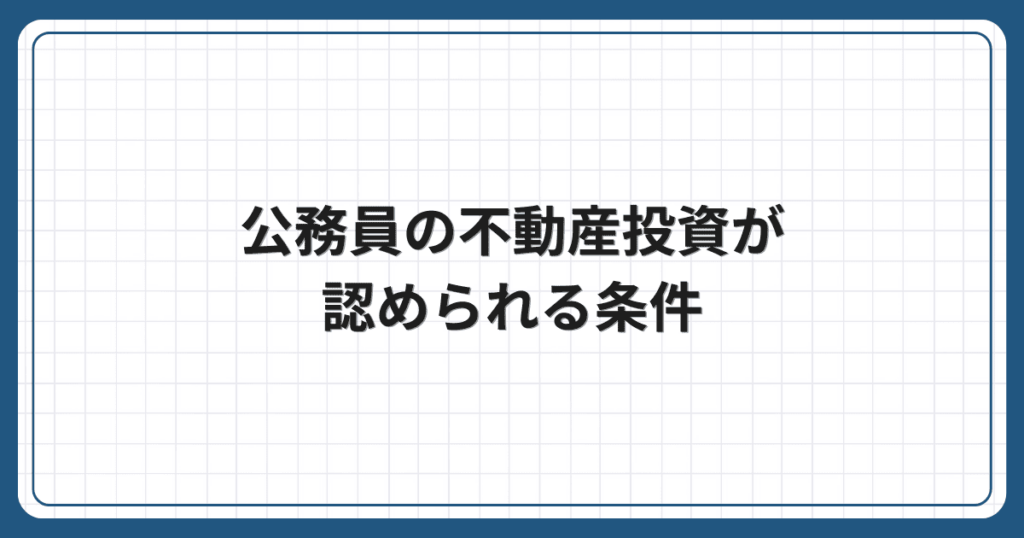
公務員の不動産投資が認められる条件を具体的に見ていきましょう。ただし、こちらで紹介する条件はあくまでも目安のひとつです。判断に迷う場合は、必ず所属先に確認しましょう。
規模が5棟10室未満
公務員の不動産投資において、まず目安となるのが物件の規模です。独立した戸建て住宅を貸し出す場合は5棟未満、アパートやマンションなどの集合住宅を区分所有で貸し出す場合は10室未満であれば、事業的規模に該当しないとされています。
これはいわゆる「5棟10室基準」と呼ばれ、多くの税務処理や副業規定の判断において、重要な目安になっています。この範囲内であれば、副業とみなされず、公務員でも賃貸経営を始められるでしょう。
不動産の管理を委託する
公務員が不動産投資を行ううえで、物件の管理方法も重要なポイントです。公務員が自分で入居者の募集や対応、家賃の集金などを直接行う場合、労働とみなされ副業に該当する可能性が高くなってしまいます。
そこで推奨されるのが、管理会社に管理業務を委託することです。家賃の集金や入居者からのクレーム対応などを専門業者に任せることで、公務員自身が直接的に管理業務に関与する必要がなくなり、本業への影響を最小限に抑えられます。
管理費はかかりますが、副業とみなされるリスクを低減し、安心して不動産投資を続けられるのは大きなメリットだといえるでしょう。
賃料収入が年間500万円未満
不動産投資による賃料収入の金額も、副業とみなされるかの判断基準です。一般的に、年間の賃料収入が500万円未満であれば、継続的に収入を得る目的の経営とはみなされにくいです。
例えば、月額家賃40万円程度の収入であれば年間480万円になり、この基準内に収まります。なお、500万円という基準は収入から諸経費を差し引いた所得ではなく、家賃や駐車場代などを含む総収入ベースで判断されることを覚えておきましょう。
申請すれば条件外でも不動産投資が認められることがある
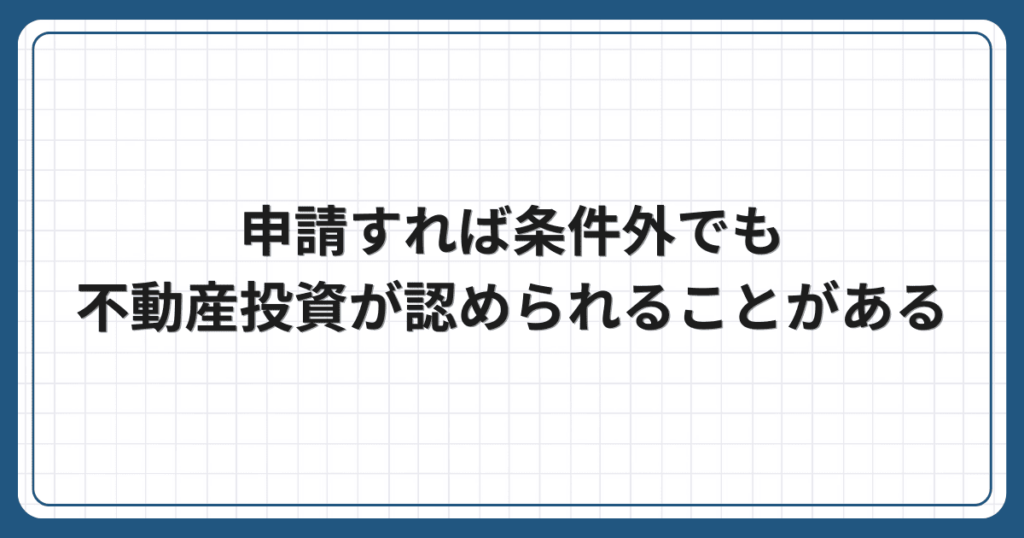
5棟10室基準や年間家賃収入500万円未満といった条件から外れる場合でも、申請により認められるケースがあります。ここでは、申請が通りやすいケースと申請手続きについて解説します。
申請が通りやすいケース
申請が通りやすいケースには、下記の2つがあります。
- 相続によって物件を取得した
- 本業との利益相反がない
代表的なのは、相続によって不動産を取得した場合です。親や親族から不動産を相続したケースは、自ら積極的に不動産事業を始めたわけではないため、やむを得ない事情として認められやすいでしょう。
また本業との利益相反がなく、公務員としての信用や職務の公正さを損なわない場合も、申請が通りやすい傾向にあります。例えば、勤務時間外に行われ、本業にまったく支障がないケースなどが該当します。
副業の申請手続き
不動産投資を副業として行う場合は、まず「自営兼業承認申請書」を作成し、所属する省庁などに提出します。国家公務員の場合、申請書を提出して問題がなければ人事院の承認を得るのが一般的な流れです。
地方公務員は所属部署の上司を経由して、人事担当部署へ提出するのが一般的です。
申請書には、不動産投資の具体的な内容や管理方法などを記載します。承認を得るまでには一定の時間がかかるため、早めに準備を進めることが大切です。
副業に該当する大規模な不動産投資を始めてしまうと、後々問題になる可能性があるため、必ず正規の手続きを踏むようにしましょう。
公務員に不動産投資がおすすめな5つの理由
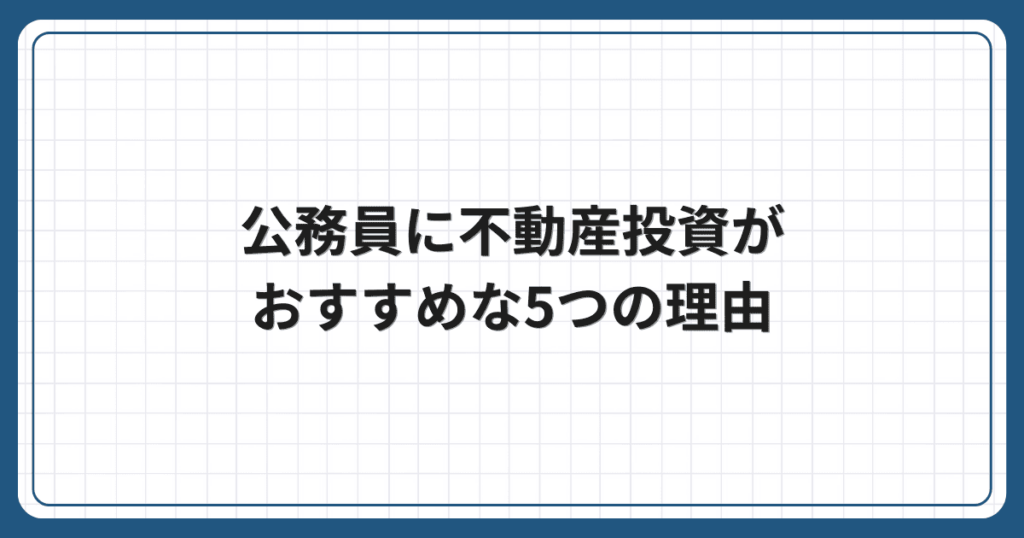
公務員という安定した立場は、不動産投資を始めるうえで大きなメリットとなることがあります。ここでは、公務員に不動産投資がおすすめな理由を5つ解説します。
与信が大きくローン審査が通りやすい
公務員の最大のメリットのひとつは、社会的信用の高さと収入の安定性です。公務員は金融機関からの与信評価が高く、不動産投資のためのローン審査が有利に進む傾向にあります。金融機関は融資先の返済能力を重視するため、景気に左右されにくく、失業リスクも低い公務員は優良な顧客とみなされやすいのです。
また、場合によっては物件価格の全額を借入するフルローンも視野に入ってきます。フルローンを利用することで、自己資金が少なくても収益物件を購入できる可能性があります。
個人の借入状況や物件の評価にもよりますが、他の職業と比較して不動産投資ローンを組みやすい点は、公務員が不動産投資を始めるうえで大きなアドバンテージといえるでしょう。
安定収入で返済計画が立てやすい
公務員は民間企業と比較して雇用が安定しており、定年まで継続的な収入が見込めます。安定収入が期待できるのは、不動産投資におけるローンの返済計画を立てるうえで、非常に重要なポイントです。
また、生活費や教育費など他の出費とのバランスも取りやすく、計画的な資産形成がしやすい点も強みです。突発的な出費が発生しても、安定収入があることで冷静に対処でき、家計全体を大きく崩すことなくローンを継続できる安心感があります。
公務員であること自体が、長期的な不動産運用における信頼性の証となりうるのです。
老後の資産形成に有効である
年金制度が不安視される近年では、老後の生活費を公的年金だけでまかなうことに不安を覚えている人も多いでしょう。その点、不動産投資による家賃収入は定年後も継続して得られる不労所得であり、年金の補完的な収入源として非常に有効です。
加えてローン返済を退職前に完了させておけば、退職後はほぼ家賃収入がそのまま手取り収入になるため、生活に余裕を持たせられます。
また、不動産はインフレに強い資産です。長期保有によって土地や建物の価値が上がれば、売却益(キャピタルゲイン)を得るチャンスもあります。
このように、不動産投資は公務員の老後の資産形成における強力な選択肢となるのです。
生命保険代わりになる
不動産投資ローンを契約する際には、多くの金融機関が団体信用生命保険(団信)の加入を義務付けています。団体信用生命保険は、ローン契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、保険金によって残りのローンが全額弁済されるという保険です。
ローン契約者に万が一の事態が起こっても、家族には借金の負担が残らず、不動産という形の資産をそのまま相続できます。不動産投資が生命保険の代替機能としても活用できることは、公務員にとって大きな魅力です。
節税効果が期待できる場合がある
不動産投資で得られる所得は、家賃収入から減価償却費や固定資産税などの必要経費を差し引いて計算されます。この不動産所得が赤字になった場合、給与所得など他の所得と損益通算することで課税所得を圧縮し、所得税や住民税の節税効果が期待できます。
特に、収益物件購入初年度は諸費用が多くかかるため、赤字計上しやすいです。ただし、節税目的だけでなく、あくまで健全な不動産経営を心がけることが大切です。
また、節税を実現するためにも、忘れずに確定申告をしましょう。
【この記事を読んだ人にはこちらもオススメ】



公務員の不動産投資の成功例・失敗例
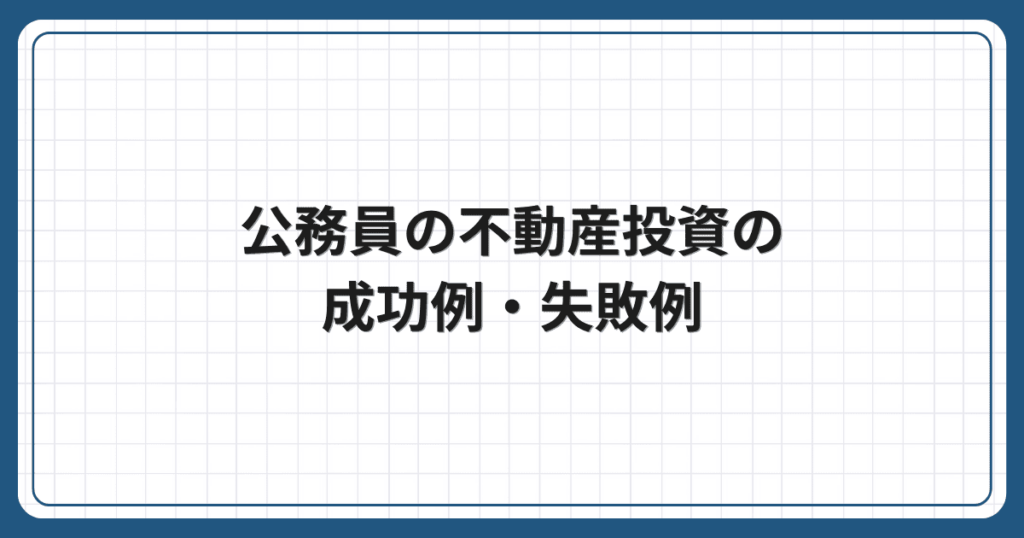
公務員が不動産投資で成功するためには、成功例とともに失敗例も知っておくことが重要です。ここでは、公務員の不動産投資の成功例と失敗例を解説します。
公務員の不動産投資の成功例
公務員の不動産投資の成功例を3つ紹介します。
公務員の不動産投資の失敗例
続いて、公務員の不動産投資の失敗例も3つ紹介します。ただし、このような失敗は知識不足や業者任せにしていることが原因のケースがあります。
不動産投資の知識を身につけたり、自分で適切な判断を下せるようになったりすれば、十分に避けられるでしょう。
公務員が不動産投資で失敗しないためのポイント
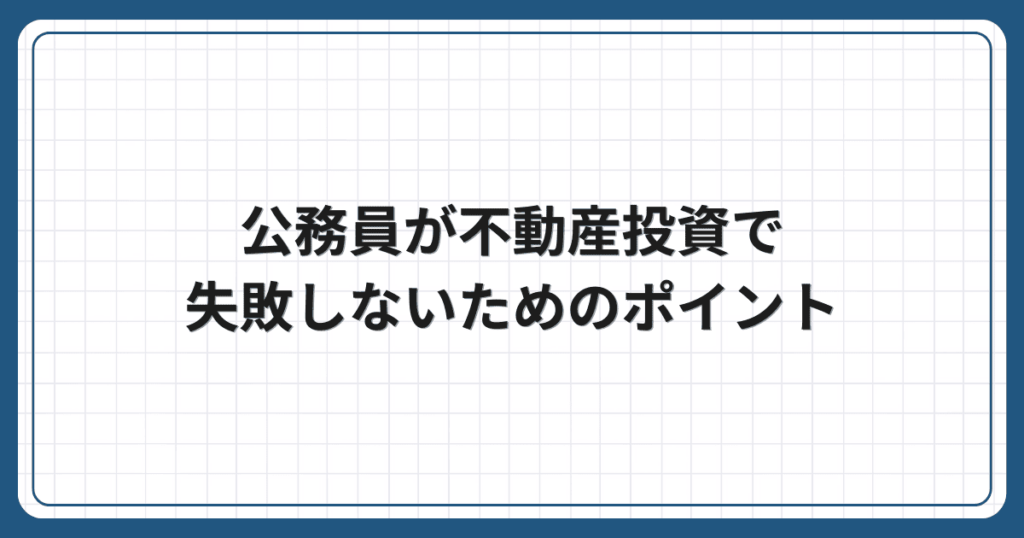
公務員は不動産投資で有利な点が多い一方で、失敗するケースもあります。ここでは、公務員が不動産投資で成功を収めるために、特に押さえておきたい4つのポイントを解説します。
不動産投資の基礎知識を身につける
不動産投資は、物件を購入して家賃収入を得るというシンプルな構造に見えますが、実際には多くの専門知識や判断力が求められる投資手法です。購入価格や利回り、空室リスクなどの幅広い要素を理解しておかないと、思わぬ損失を被ることもあります。
そのため、投資を始める前には必ず書籍やYouTube動画、セミナーなどから体系的に学ぶことが重要です。特に公務員の場合、副業規定に抵触しない方法も併せて学ぶ必要があり、一般的な投資家以上に慎重な姿勢が求められます。
まずは正しい知識という土台を築きましょう。
法令遵守を徹底する
公務員は国家公務員法や地方公務員法に基づき、副業や兼業に制限が設けられています。不動産投資も規模や関与度によっては副業とみなされる場合があり、懲戒処分や減給といったペナルティの対象になる恐れがあります。そのため、法令や規定を正しく理解し、違反しないよう最大限の注意を払うことが不可欠です。
具体的には、5棟10室未満や管理業務の外注など、公務員が不動産投資を行ううえでの基準を遵守しましょう。また、必要に応じて確定申告も正確に行う必要があります。
迷った場合は上司に事前相談することで、リスクを回避できます。規則を守りながらも利益を得る工夫が、不動産投資で成功するカギです。
無理のない投資計画を立てる
不動産投資では物件価格やローン返済額、修繕費用などを踏まえたうえで、現実的な投資シミュレーションを行うことが成功の第一歩です。特に公務員は副業制限があるため、大規模な収益物件や事業的規模の投資はリスクが高く、資金計画を慎重に立てる必要があります。
投資計画では自身の手取り収入や支出バランス、今後のライフイベントなどを考慮し、無理のない範囲で返済が可能かをシミュレーションすることが大切です。また物件購入後も突発的な出費に備えて、生活資金とは別の緊急予備費を確保しておくことがリスクヘッジになります。
信頼できるパートナーを選ぶ
不動産投資を成功させるためには、専門家のサポートをうまく活用することも重要です。特に初心者の場合は、優良物件かどうかの判断がつかないことも多く、不動産会社の提案に依存しがちになります。そのため、知識だけでなく顧客対応やアフターフォロー体制などを含めて、信頼できる業者を選定するようにしましょう。
また、物件の管理については、頼りになる管理会社を選ぶことが大切です。特に公務員の場合、本業との両立のため、物件管理の負担を最小限に抑える必要があります。実績のある管理会社を選ぶことで、長期的に安定した運用体制を築きやすくなります。
不動産投資で利益が出たら公務員も確定申告が必要
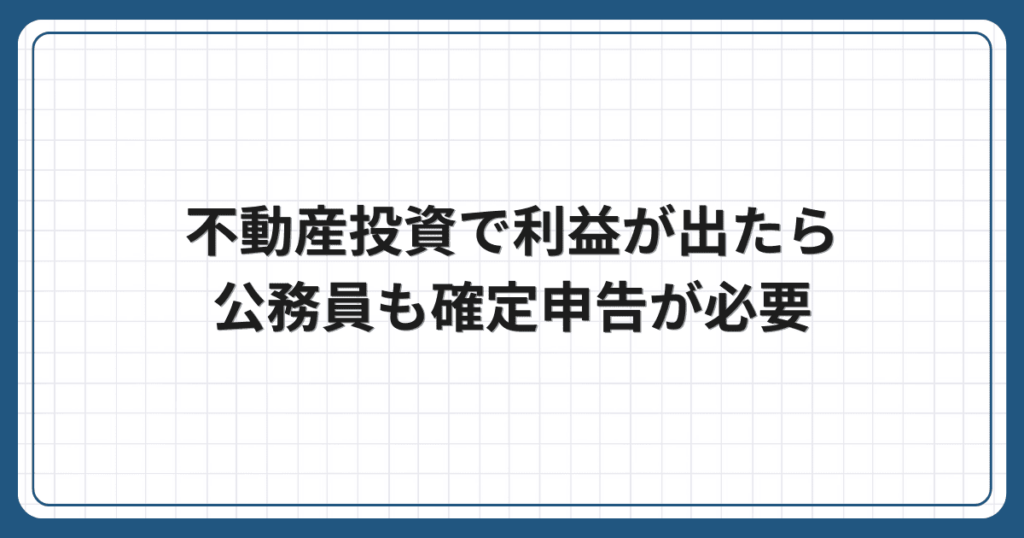
公務員は年末調整を行うため、基本的には確定申告は必要ありません。しかし、不動産投資によって利益が生じた場合は話が別です。家賃収入から修繕費や管理費などの必要経費を差し引いた不動産所得が年間20万円を超える時は、確定申告を行う必要があります。
確定申告を怠ると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があるため注意が必要です。申告期間内に正確な申告を行うようにしましょう。
また事業規模の不動産投資をしている場合、許可を得ていない不動産収入が発覚すると、懲戒処分のリスクがあります。心配であれば、所属組織の上司や人事担当部署に相談し、正式な手続きを行うようにしてください。
不動産投資の確定申告のやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

公務員の不動産投資にはプロパリー
引用元:プロパリー
| 価格 | 無料 |
| 対応OS | iOS/Android |
| 4つの強み | プロを比較して選べる 将来の収支予測 リアルタイム収支管理 買主から直で売却オファー |
公務員として不動産投資を始めるには、法律の制約や規模の制限をしっかりと把握し、ルールを守った運用が欠かせません。さらに管理業務を自分で行わないなど、注意すべきポイントも多く、正しい知識と計画的な運用が必要です。
そこで活用したいのが、不動産投資サービスの「プロパリー」です。プロパリーに登録すると、登録内容に応じたオファーが複数のプロフェッショナルから送られてきます。
不動産投資のプロは公務員の副業規定にも配慮しながら、資産形成の第一歩を丁寧にサポートします。管理業務の委託やローン審査へのアドバイスなどに対応してくれるため、初めての投資でも安心です。
プロパリーを利用することで、頼りになるパートナーが見つかります。プロパリーの利用料はかかりません。堅実な不動産投資をパートナーとともに進めたい公務員は、この機会にプロパリーをダウンロードしましょう。
公務員の不動産投資に関するよくある質問
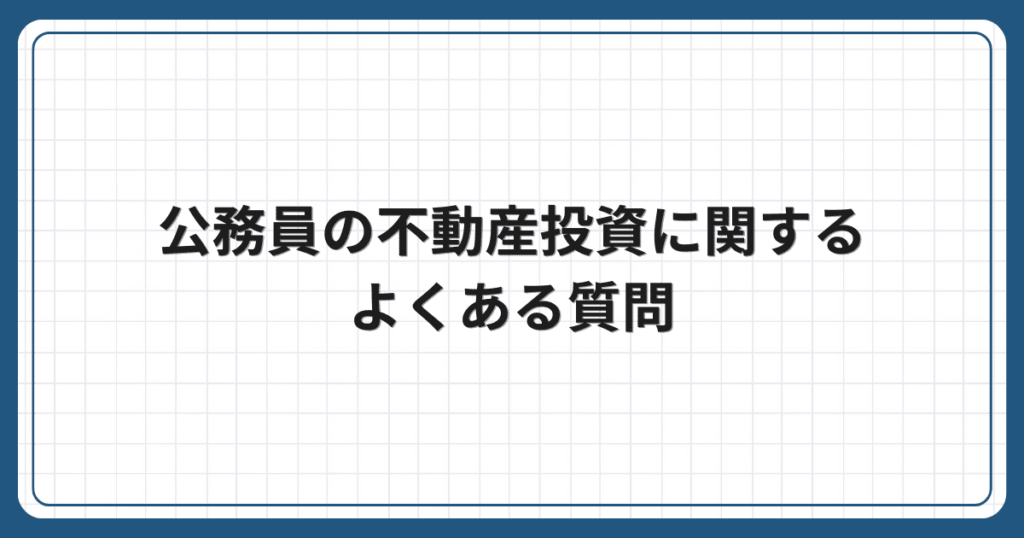
公務員の不動産投資に関するよくある質問について回答します。
- 公務員の不動産投資で参考になるブログやYouTubeはある?
-
ブログ「元公務員ママ大家 早期退職のすすめ」では、元公務員のCHITO氏が不動産投資を始めた理由などを説明しています。
また、YouTube「公務員が自力で稼げるチカラをつけるch」では、公務員の不動産投資の始め方や不動産業者の見分け方などについて解説しています。
実体験に基づく具体的なノウハウや注意点などを公開しているブログやYouTubeを探してみるとよいでしょう。
- 公務員は不動産投資でカモにされやすい?
-
公務員だからといって、一概にカモにされやすいわけではありません。ただ、公務員は安定した収入があり融資を受けやすいため、不動産業者から積極的にアプローチされることがあります。
特に投資経験が少ない公務員は「安定した収入がある公務員なら大丈夫」という甘い言葉に乗せられ、収益性の低い物件を購入してしまうリスクがあります。自己防衛のためにも、事前に知識を身につけ、複数の業者を比較する姿勢が大切です。また、信頼できる専門家や経験者に相談することも有効です。
- 公務員の不動産投資は勤務先にバレる?
-
公務員の不動産投資が勤務先にバレるかどうかは、規模や運営方法などによります。例えば5棟10室未満で管理委託しており、職務に支障なく行っていれば、バレるリスクは低いでしょう。
また、確定申告による住民税の納付方法を普通徴収にすることで、勤務先にバレるリスクを低減できます。適切な運用方法を選択し、正しい知識を身につけることが重要です。
- 不動産投資がうまくいったら、公務員でも法人化できる?
-
公務員でも不動産投資の法人化は可能です。収益が増加した場合、節税対策やさらなる事業拡大のために法人化を検討するケースがあります。ただし、法人化すると事業としての性格が強まるため、公務員の副業規制に抵触する可能性があることに注意が必要です。
法的リスクを回避するためには、事前に上司や専門家に相談することが必須です。
まとめ:不動産投資は公務員向き!まずはプロパリーへ
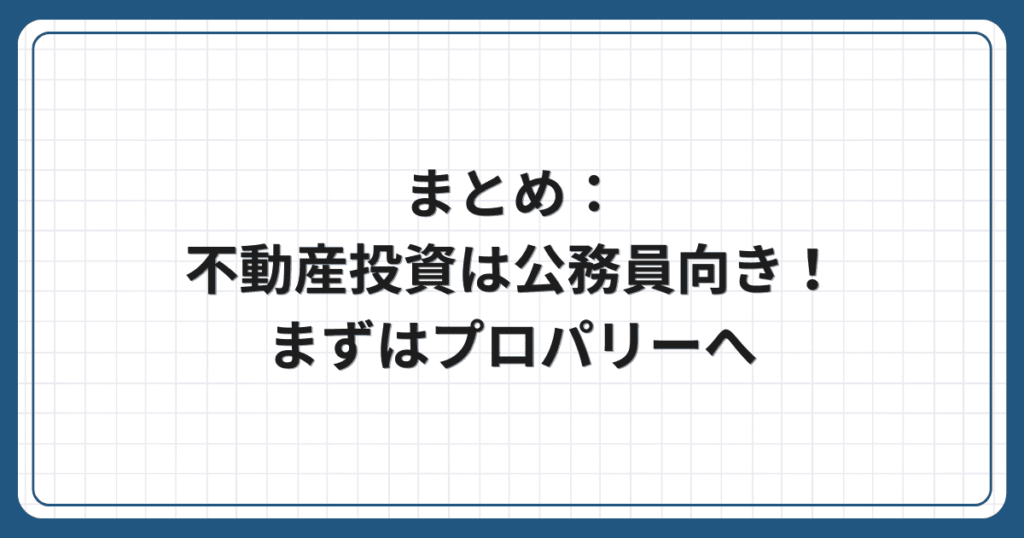
公務員は社会的信用の高さと収入の安定性が金融機関から評価されやすいため、不動産投資を始めやすいです。ただし、規模が5棟10室未満で不動産の管理を委託するなどの条件を守らなければ、副業とみなされる可能性もあります。
不動産投資を始めたい公務員におすすめしたい不動産投資サービスがプロパリーです。プロパリーでは、厳しい審査基準をクリアした不動産投資のプロから公務員の登録情報に適したオファーが届きます。
実績のある管理会社の紹介などにも対応可能なので、安心して不動産投資を始められます。プロパリーの利用料はかかりません。規則を遵守しつつ安全に不動産投資を始めたい公務員は、プロパリーをダウンロードして専門家の力を借りながら着実に進めていきましょう。