「不動産投資で加入する団体信用生命保険が生命保険代わりになると聞いたけど、本当なの?」
「団体信用生命保険の仕組みについて詳しく知りたい」
「不動産投資で加入すべき保険には何があるの?」
団体信用生命保険によって、不動産投資は生命保険の代わりになります。しかし団信だけでは、十分とはいえません。
不動産投資には火災や地震、家賃滞納などのリスクもあるため、適切な保険への加入が不可欠です。
本記事では、生命保険代わりといわれる仕組みから、不動産投資に不可欠な各種保険の役割まで、初心者にも分かりやすく徹底的に解説します。本記事を読むことで、自分が備えるべきリスクが分かり、対応する最適な保険を選べるようになります。

不動産投資するならプロパリー・資産管理・物件シミュレーション
誰でも完全無料で、不動産投資の基本から実際の購入・運用まで詳しく学べる学習アプリです。
プロパリーは不動産会社ではないからこそ、物件を売りたいだけの業者には伝えられない、真実の情報を提供しています。
不動産投資は生命保険の代わりになる
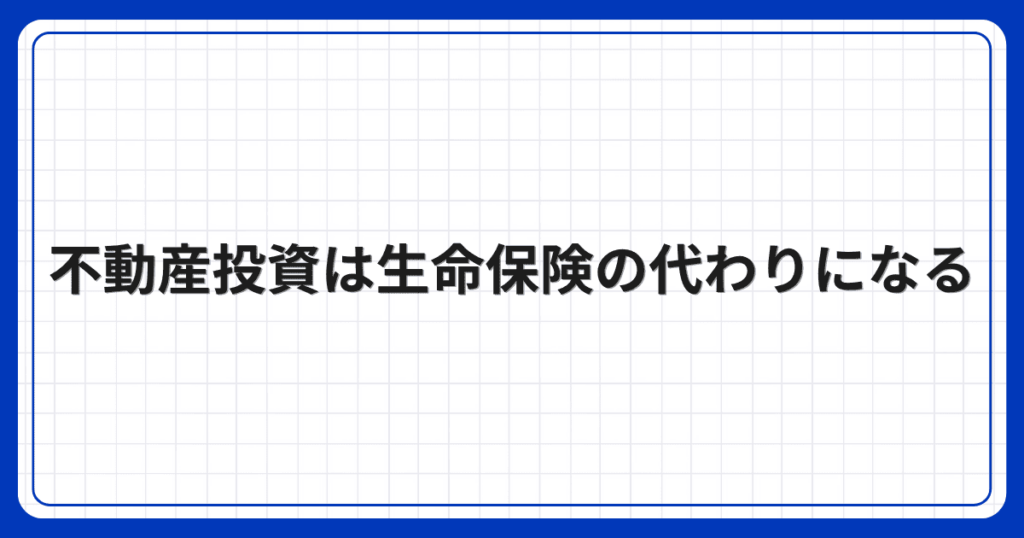
不動産投資ローンを組んで物件を購入すると、多くの場合「団体信用生命保険(団信)」への加入が求められます。この団信の仕組みこそが、不動産投資が生命保険代わりといわれる最大の理由です。
万が一のことがあった際に、残された家族に金銭的な負担をかけることなく、収益を生む資産を残せる可能性があります。ただし、現金給付がある一般的な生命保険とは役割が異なる点に注意が必要です。
ローンの返済が免除される
団体信用生命保険に加入していれば、契約者が死亡または高度障害状態になった場合、残りのローン返済が免除されます。例えば、3,000万円のローンが残っていても、保険会社が金融機関に残債を支払うため、遺族は残ったローンを借金として引き継がずに済みます。
通常の生命保険のように現金が遺族に支払われるわけではありませんが、巨額の負債がなくなるという点で、非常に大きな経済的保障といえるでしょう。遺族が借金を相続する心配がなくなるのは、計り知れない安心材料です。
ただし、保険適用には一定の条件があるため、事前に保険内容を確認することが重要です。
遺族が家賃収入を得られる
ローンが完済された物件は、遺族にとって安定した収入源になります。その物件に入居者がいれば、家賃収入が継続して得られます。例えば、月10万円の家賃が入れば、年間で120万円の収入が見込めるでしょう(空室リスクや修繕費などの運営コストを省いた計算)。
このお金は、遺族の生活費や子どもの教育費に充てられ、経済的な安心感につながります。ただし、空室や家賃下落のリスクもあるため、立地や物件の質には十分な配慮が欠かせません。適切な物件選びと管理を行えば、長期にわたり収益性を保つことが可能です。
家賃収入については、こちらの記事で詳しく解説しています。
家賃収入とは?不動産投資だけで生活できる?収益を増やすコツや税金対策を解説
物件を売却して利益を得られる
遺族は、相続した無借金の収益物件を賃貸経営し続けるだけでなく、売却してまとまった現金に換えるという選択も可能です。市場の状況や立地条件によっては、購入時よりも高く売却できる場合もあります。
例えば、2,000万円で購入した物件が数年後に2,500万円で売却できれば、500万円の売却益を得られます(諸経費や税金等を含まない計算)。残された家族が賃貸経営に不安を感じる場合や、子どもの教育資金あるいは住宅の購入資金など、まとまったお金が必要になった際に、この売却益が大きな助けになるでしょう。
購入時よりも高く売却するためには、売却タイミングや市場動向を見極めることが重要です。
団体信用生命保険の仕組み
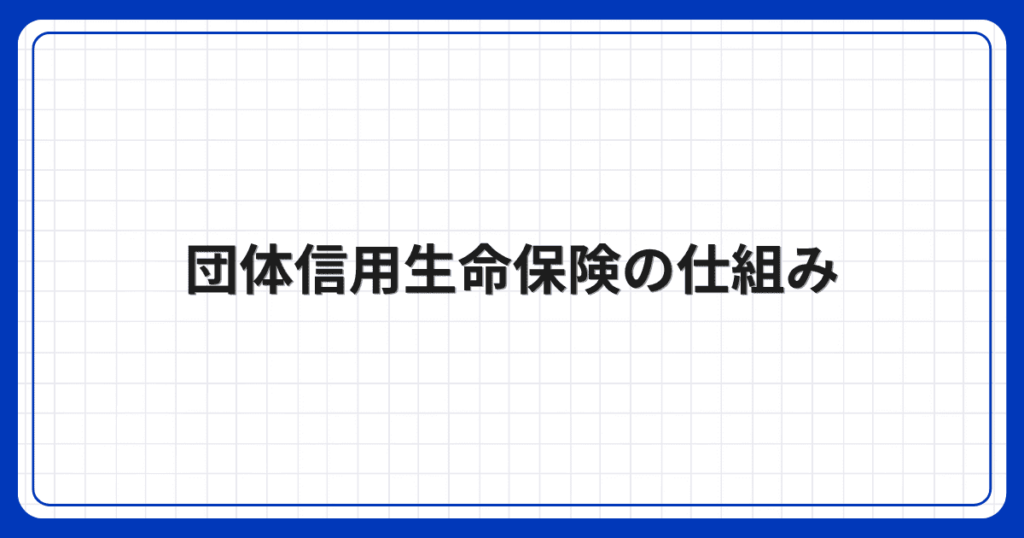
団体信用生命保険は、不動産投資ローンにおいて重要な保険です。契約者に万が一の事態が発生した場合の保障内容や加入条件について、詳しく確認していきましょう。
団体信用生命保険を含む、不動産投資で知っておくべき知識を効率よく勉強できるのが学習アプリ「プロパリー」です。物件販売業者ではないからこその具体的かつ効果的なノウハウが学べ、不動産投資の成功率を高められます。
不動産投資をやるべきか迷っているなら、まずはそのメリットを正しく知ることから始めませんか? プロパリーの利用は無料です。今すぐインストールして、ここだけの情報をゲットしてください。

不動産投資するならプロパリー・資産管理・物件シミュレーション
誰でも完全無料で、不動産投資の基本から実際の購入・運用まで詳しく学べる学習アプリです。
プロパリーは不動産会社ではないからこそ、物件を売りたいだけの業者には伝えられない、真実の情報を提供しています。
団体信用生命保険とは
団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンや投資用ローンの契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、保険会社がローンの残債を金融機関に支払う保険です。この保険により、契約者の家族がローンの返済義務を負うことはありません。
団信は住宅ローンでは付帯が一般的ですが、不動産投資ローンでは金融機関によって取り扱いが異なり、任意加入や非対応の場合もあります。また、保障内容や適用条件は、金融機関や保険プランによって異なるのが特徴です。
一部の団信では死亡時だけでなく、がんや心筋梗塞、脳卒中などの重大な疾病にも対応する特約がついている場合もあります。特約付き団信は、リスクに対する備えとしてより手厚い反面、金利への上乗せが発生するため、コストとのバランスを検討することが大切です。
団体信用生命保険には必ず加入しなければならない?
不動産投資ローンでは、団体信用生命保険への対応が金融機関によって異なりますが、多くのケースでは加入が義務づけられています。これは、貸し倒れのリスクを回避する目的もあり、保険に加入することでローン契約者に万が一のことが起きても残債が回収できるためです。団信は、金融機関にとっても契約者にとってもメリットがある仕組みといえるでしょう。
団信への加入が必要かは、利用する金融機関やローンの種類によって異なります。ローン申請前には、団信の加入条件や保障内容、金利への影響などをしっかり確認しておくようにしましょう。
団体信用生命保険の加入条件
団体信用生命保険には、一般的な団信と加入条件が緩和されたワイド団信の2種類に分けられます。それぞれの特徴を見てみましょう。
| 一般団信 | ワイド団信 | |
|---|---|---|
| 年齢制限 | 20歳以上70歳未満(金融機関によって異なる) | 20歳以上65歳未満(金融機関によって異なる) |
| 健康告知 | 病気・手術歴、現在の健康状態を詳細に申告する | 簡素化された健康告知でよい |
| 加入審査 | 厳格な健康審査が行われる | 一般団信よりも緩和された健康審査が行われる |
一般団信への加入には、健康状態に関する告知が必要です。一般団信では厳格な健康審査が行われ、持病がある場合は加入を断られる可能性があります。
健康状態に不安がある人は、加入条件が緩和されたワイド団信を選択することで、より柔軟な審査を受けられます。ただし、ワイド団信は一般団信よりも金利が高めに設定される傾向があるため、ローン全体のコストに与える影響が大きくなりやすい点に注意が必要です。
健康状態に不安がある人は、ローンの仮審査を受ける前に、団信の加入条件について金融機関に事前に相談しておくとスムーズです。また、複数の金融機関で条件を比較検討することも、選択肢を広げるひとつの方法といえます。
団体信用生命保険の保険料はいくら?
一般的に住宅ローンでは、団体信用生命保険の保険料は金利に含まれており、借り手が別途支払う必要はありません。ただし、不動産投資ローンでは別途保険料が必要なケースもあるため、契約内容を事前に確認しましょう。
金利に上乗せされる部分は、通常0.1%〜0.3%程度です。例えば、2,000万円のローンを組んだ場合、年間の保険料相当額は2万円〜6万円程度になります。
三大疾病保障付きや八大疾病保障付きの団信を選択する場合は、さらに0.1%〜0.3%程度の金利上乗せが発生します。ワイド団信の場合は、通常の団信よりも0.2%〜0.3%ほど高い金利設定となることが多いです。
保険料は借入残高に応じて変動するため、ローンの返済が進むにつれて実質的な保険料負担は軽減されます。
団体信用生命保険と生命保険(死亡保険)の違い
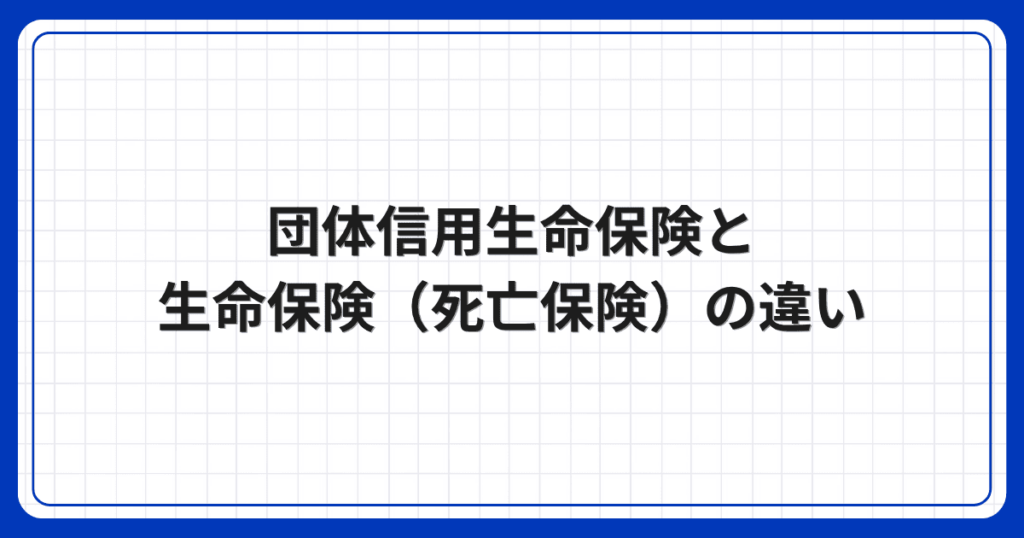
団体信用生命保険と一般的な生命保険には、加入目的や保険金受取人などに明確な違いがあります。それぞれの特徴を正しく理解し、自分や家族のライフプランに適した保障内容を選択することが、将来的な安心につながります。
| 団体信用生命保険 | 一般的な生命保険 | |
|---|---|---|
| 加入目的 | ローン債務の返済 | 遺族の生活保障 葬儀費用 教育資金 など |
| 保険金受取人 | 金融機関 | 契約者が指定した遺族など |
| 保険金額 | ローン残高に連動して減少する | 契約時に設定した金額で一定 |
| 保険料の支払方法 | 金利に含まれる | 別途支払いが必要 |
| 加入条件 | ローン契約が前提 | 単独で加入可能 |
団体信用生命保険に入れば生命保険は不要?
団体信用生命保険に加入したからといって、すべての生命保険が不要になるわけではありません。そもそも団信は、不動産投資ローンの残債を肩代わりすることに特化した保険です。
契約者が死亡または高度障害状態になったときに、ローンが完済される仕組みのため、物件自体や家賃収入といった資産は遺族にそのまま引き継がれます。この点において、団信は一部生命保険のような役割を果たすといえます。
しかし、団信のみでは遺族の生活費や子どもの学費、葬儀費用といった日常的・突発的な支出までカバーできるわけではありません。そのため、遺された家族の生活に対して広範囲にわたる備えをしたい場合は、団信だけでは不十分なケースが多くあります。家賃収入だけで生活費を賄えない場合は、追加の生命保険への加入を検討すべきでしょう。
また、団信は高度障害状態での保障が中心のため、働けなくなった場合の収入保障としては不十分なケースがあります。総合的なリスク管理の観点から、団信と生命保険を組み合わせた保障設計が重要です。
サラリーマンは不動産投資すべき?失敗例や成功のコツ・確定申告の必要性を解説
団体信用生命保険のほうが生命保険よりもお得?
団体信用生命保険と生命保険のどちらがお得かは、個人の状況によって異なります。団信は保険料が金利に含まれているため、支払負担を感じにくい一方で、生命保険は保険料控除の対象となり節税効果がある点が魅力です。
例えば、年間8万円の生命保険料を支払っている場合、所得税では最大4万円、住民税では最大2.8万円が所得控除されます(節税額は課税所得や税率によって異なる)。また、生命保険には解約時に返戻金を受け取れるタイプもあり、資産形成の手段として活用されることもあります。
一方で、団信はあくまでローン返済を保障するための保険であり、解約返戻金などの資産価値はありません。若い世代であれば、生命保険の保険料のほうが団信より割安になるケースもあります。
自分にとってどちらが適しているかは、年齢や健康状態、家族構成などを踏まえて判断することが大切です。
不動産投資をやるなら加入すべき保険
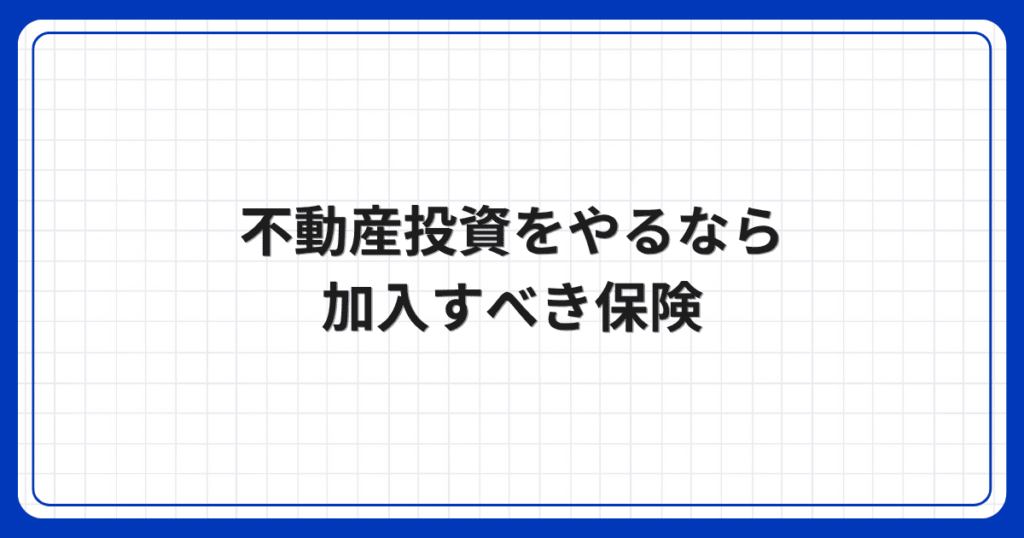
投資用物件のオーナーになると、自分の生死リスクだけでなく、物件そのものに関わるさまざまなリスクに備える必要があります。ここでは団体信用生命保険以外に、加入を検討すべき重要な保険を紹介します。
火災保険
火災保険は、建物や家財を火災や自然災害から守る保険です。不動産投資では、物件の損害が直接収益に影響するため、必ず加入すべき保険といえるでしょう。なお、一般的にはローンを組む際に加入が義務づけられることが多く、ほとんどの不動産オーナーが契約しています。
火災だけでなく落雷や爆発、風災なども補償対象です。保険料は建物の構造や立地、保険金額によって決まり、木造建物よりも鉄筋コンクリート造のほうが安くなります。
また、火災だけでなく水濡れや盗難、破損・汚損などを補償対象に含められる商品もあります。補償範囲は保険会社や契約プランによって異なるため、物件のリスクに応じて適切な内容を選びましょう。
地震保険
地震保険は地震や噴火、津波による損害を補償する保険です。火災保険とセットで加入する必要があり、単独では加入できません。日本は地震大国であり、大規模地震のリスクは常に存在するため、不動産投資においても重要な保険です。
保険金額は火災保険の30%〜50%の範囲で設定され、建物の構造や所在地によって保険料が決まります。木造建物のほうが、鉄筋コンクリート造よりも保険料が高く設定されています。また、各都道府県の地震リスクに応じて保険料率が異なるため、立地によって負担額が変わることも特徴です。
さらに、地震保険料は所得税・住民税の控除対象です。節税面でもメリットがあるので、地震が多い地域の物件を所有している不動産オーナーは、加入を検討するとよいでしょう。
施設賠償責任保険
施設賠償責任保険は、物件の欠陥や管理不備により第三者に損害を与えた場合の賠償責任をカバーする保険です。例えば、建物の外壁が剥がれて通行人にけがを負わせた場合や、共用部分の清掃不備により入居者が転倒したケースなどが対象になります。損害賠償額が高額になることもあるため、万が一の備えとして加入しておくと安心です。
保険料は補償額や物件規模によって異なりますが、小規模物件であれば年間数千円から契約可能な商品もあります。もしもの事故に備え、火災保険のオプションとして付帯できるケースも多いため、併せて検討することをおすすめします。
家賃保証
家賃保証は、入居者が家賃を滞納した際に、保証会社が一定期間家賃を立て替えてくれる制度です。入居者に加入してもらうのが一般的で、不動産オーナーは家賃滞納のリスクを大幅に軽減できます。
ただし、保証会社によって保証内容や対応が異なるため、信頼できる会社を選択することが重要です。
不動産投資の保険に関するよくある質問
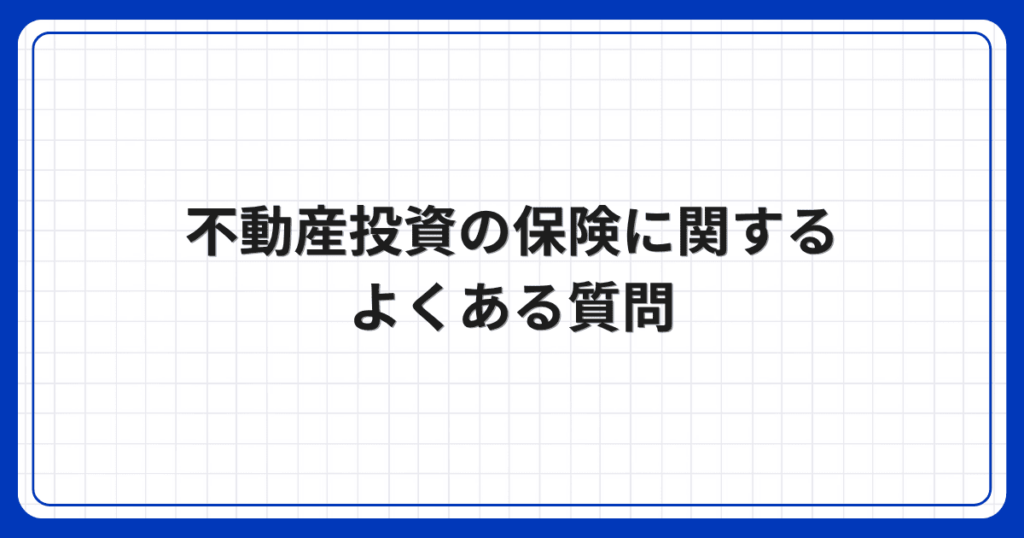
不動産投資の保険に関するよくある質問について回答します。
- 不動産投資の保険料は経費になる?
-
不動産経営に必要な保険料は、確定申告の際に必要経費として計上できます。具体的には、火災保険料や地震保険料、施設賠償責任保険の保険料などが該当します。
不動産投資×税金|知らないと損する税知識と節税のコツをプロが徹底解説
ただし、保険期間が1年を超える場合は、支払った保険料を保険期間で按分して各年度の経費にする点に注意が必要です。例えば、5年分の火災保険料50万円を一括で支払った場合は、年間10万円ずつ経費計上します。
団信の保険料については、ローンの利息に含まれているため、支払利息として経費計上することになります。
- 不動産投資で保険にまったく入らなかったらどうなる?
-
ローンを利用して物件を購入する場合、金融機関から担保価値保全のために火災保険への加入が義務づけられるケースがほとんどです。そのため、保険にまったく入らないというケースは現実的ではありません。
仮に現金一括購入などで無保険状態だった場合、火災や自然災害で建物が全壊・全焼すると資産価値はゼロになり、再建費用もすべて自己負担になります。当然、その間の家賃収入も得られません。
不動産投資は事業であり、保険は事業継続のための必要不可欠なコストです。適切な保険への加入は、不動産投資を安全に行うための最低限の条件といえるでしょう。
- 不動産投資と生命保険、節税の面でお得なのはどっち?
-
節税効果の面では、それぞれ異なるメリットがあるため、どちらがお得とは一概にいえません。生命保険は生命保険料控除により、所得税で最大4万円、住民税で最大2.8万円の控除を受けられます。
一方、不動産投資で支払う火災保険料や地震保険料などは、事業に必要な経費として全額を計上可能です。また、不動産所得が赤字になった場合は、給与所得など他の所得と損益通算することで、所得税や住民税の還付を受けられる場合があります。
節税目的だけで選ぶのではなく、自身のリスク許容度や収支計画に応じて、保険の使い分けをすることが大切です。
不動産投資を生命保険代わりにしたいならプロパリーで勉強しよう
引用元:プロパリー
| 価格 | 無料 |
| 対応OS | iOS/Android |
| 4つの強み | プロを比較して選べる 将来の収支予測 リアルタイム収支管理 買主から直で売却オファー |
不動産投資は生命保険の代わりになりますが、それはあくまで収益の出る物件を残せた場合の話です。赤字続きの売れない物件を残されても、遺族は困るだけ。
不動産投資に生命保険の役割を期待するなら、まずは学習アプリ「プロパリー」で成功ノウハウを学びましょう。不動産会社は売れ残り物件を片付けるため、特定の物件タイプを強く勧めたり、メリットを過度に強調したりすることがあります。
しかしプロパリーは物件販売業者ではないからこそ、物件や業者選びについて公平な情報の提供が可能です。「本当に良い物件の条件は何か」「信頼できる不動産会社の特徴は何か」を赤裸々に伝えているので、初心者でも本物と偽物を見分けられます。
さらに収支シミュレーションやプロへの質問など、実際に物件を検討するうえで役立つ機能も用意しています。そのためプロパリーを使いこなせば、生命保険としての役割を果たしてくれる、本当に良い物件を見つけられるのです。
プロパリーは無料で利用できます。今すぐインストールして、家族に感謝される不動産投資を始めましょう。

不動産投資するならプロパリー・資産管理・物件シミュレーション
誰でも完全無料で、不動産投資の基本から実際の購入・運用まで詳しく学べる学習アプリです。
プロパリーは不動産会社ではないからこそ、物件を売りたいだけの業者には伝えられない、真実の情報を提供しています。
まとめ:不動産投資の保険で適切なリスク管理ができる
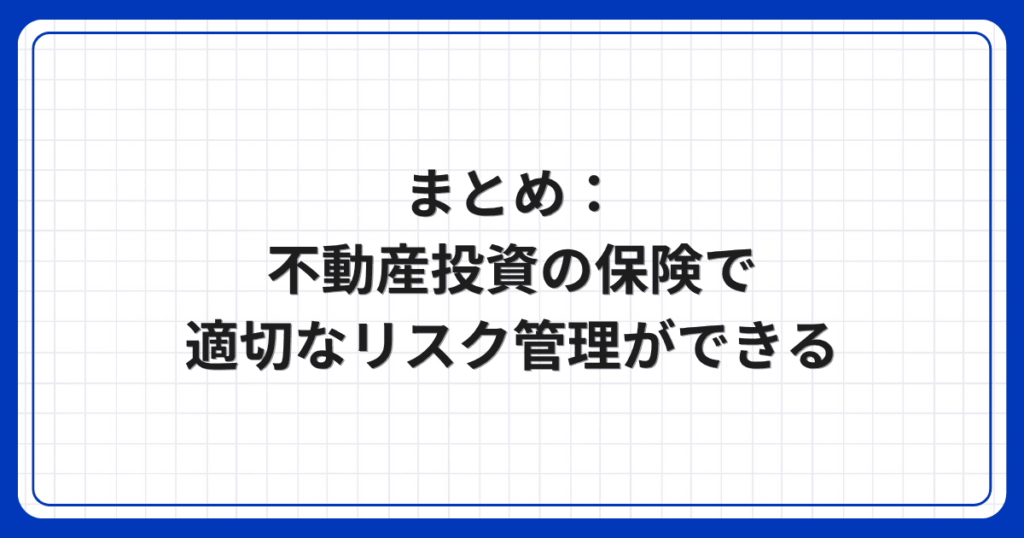
不動産投資は、団体信用生命保険により生命保険の代わりとしての機能を持ちますが、それだけでは十分ではありません。火災や地震、賠償責任といった不動産特有のリスクに備えるため、火災保険や地震保険などを適切に組み合わせることが、長期にわたって安定した資産形成を行うための条件になります。
どんな保険がどれくらい必要か考えるうえでは、不動産投資のリスクを正しく知っておくことが必要です。そこでおすすめなのが、無料の学習アプリ「プロパリー」です。
プロパリーは不動産会社ではないからこそ中立の立場で、不動産投資のデメリットやリスクも正しく伝えています。だからこそ、本当に必要なリスク管理体制も見えてくるはず。
プロパリーの利用料は無料です。不動産投資を堅実に行いたいなら、今すぐインストールしてください。

不動産投資するならプロパリー・資産管理・物件シミュレーション
誰でも完全無料で、不動産投資の基本から実際の購入・運用まで詳しく学べる学習アプリです。
プロパリーは不動産会社ではないからこそ、物件を売りたいだけの業者には伝えられない、真実の情報を提供しています。













