「所有している不動産を売却したいけど、税金は一体いくらかかるのだろう?」
「マイホームを売却すれば、税金がかからない特例があると聞いたけど、本当?」
「具体的な税額をシミュレーションして、事前に心の準備をしておきたい」
不動産売却で得た利益には税金が課されます。しかし、その計算方法は複雑で、初心者が自分一人ですべてを理解するのは容易ではありません。
仕組みを知らないまま不動産売却を進めてしまうと、本来払う必要のなかった多額の税金を納めることになったり、使えるはずの特例を見逃してしまったりする可能性があります。
本記事では、不動産売却にかかる税金の具体的な計算方法や、さまざまなケースを想定したシミュレーション、そして賢く節税するためのコツを、初心者にも分かりやすく徹底解説しました。
本記事を読めば、不動産売却時にかかる税金への理解が深まり、手残りを最大化できるようになります。
不動産売却にかかる税金の種類
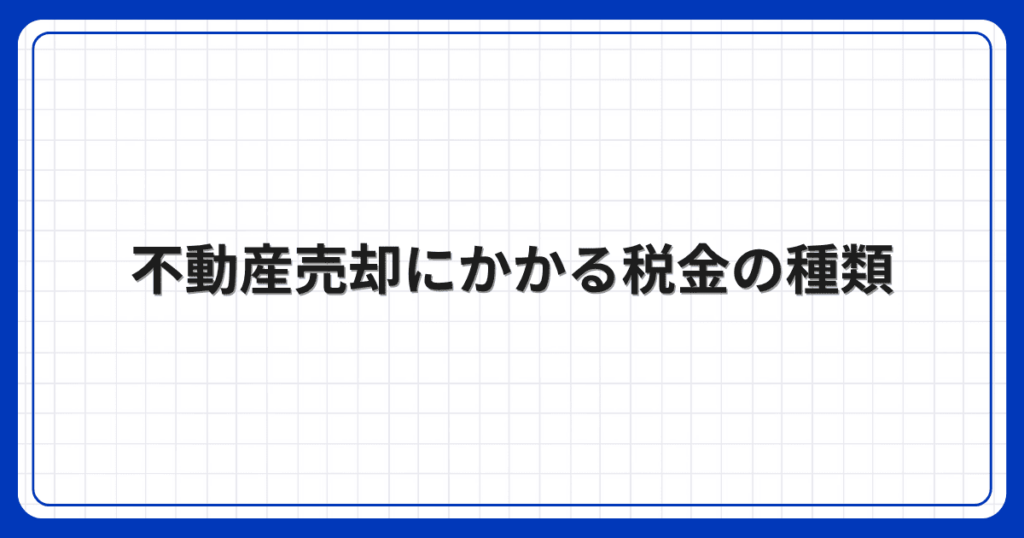
不動産を売却した際には、いくつかの税金が関係してきます。ここでは、特に重要な税金の種類について解説します。
| 税金の種類 | 税率・税額 |
|---|---|
| 譲渡所得税 | 長期譲渡所得(所有期間が5年超):20.315% 短期譲渡所得(所有期間が5年以下):39.63% |
| 登録免許税 | 不動産ひとつにつき1,000円 |
| 印紙税 | 契約書に記載された売買金額によって異なる |
売却ではなく投資に関連する税金については、こちらで解説しています。
不動産投資×税金|知らないと損する税知識と節税のコツをプロが徹底解説
譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益に対して課される税金です。所得税(復興特別所得税を含む)と住民税を合わせたものを指します。
税率は、売却した年の1月1日時点での所有期間によって、以下のように大きく異なります。
- 長期譲渡所得(所有期間が5年超):20.315%
- 短期譲渡所得(所有期間が5年以下):39.63%
登録免許税
売却する不動産に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、抵当権抹消登記の際に登録免許税がかかります。税額は、不動産ひとつにつき1,000円です。
土地と建物であれば、合計2,000円かかります。通常は、手続きを依頼する司法書士への報酬と併せて支払います。
印紙税
不動産の売買契約書を作成する際、その契約書に対して課される税金が印紙税です。契約書に収入印紙を貼付して納税します。
税額は、契約書に記載された売買金額によって異なります。例えば、売買金額が1,000万円超5,000万円以下の場合、印紙税は1万円です。
なお、2027年3月31日までは軽減措置が適用されます。
不動産売却時の税金の計算方法
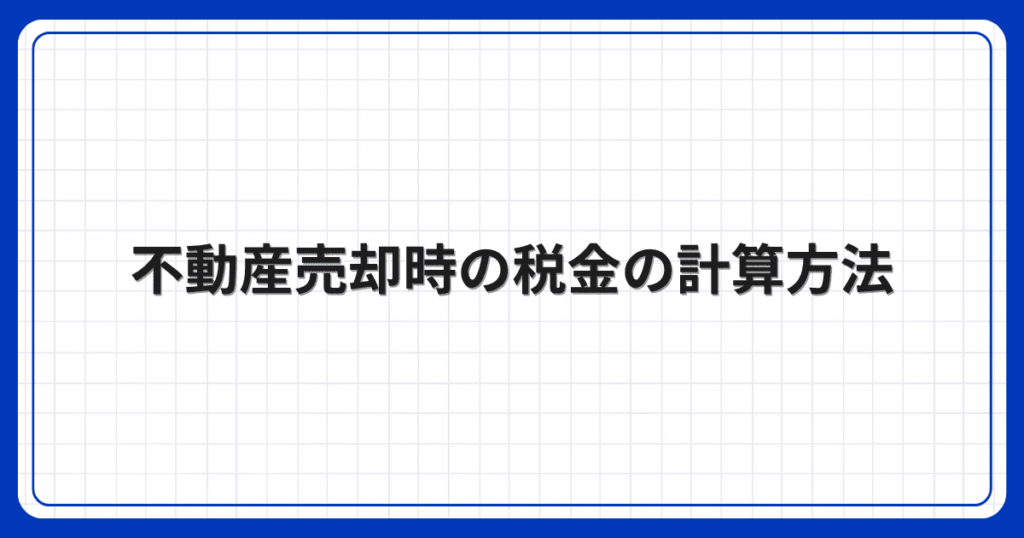
不動産売却にかかる税金を正確に算出するには、段階的な計算が必要です。
STEP1:譲渡所得の計算
まず、売却によって生じた利益(譲渡所得)を計算します。計算式は以下の通りです。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
売却価格は実際の売却金額、取得費は購入時の価格や諸費用から減価償却費を差し引いた金額です。譲渡費用は、仲介手数料や印紙税などの売却にかかった費用を指します。建物については、取得費から減価償却費を控除する必要があります。
STEP2:課税譲渡所得の計算
次に、STEP1で計算した譲渡所得から、利用できる特別控除額を差し引きます。これが、税金の計算のもとになる課税譲渡所得です。
課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除額
マイホームの売却では、3,000万円特別控除が適用できる可能性があり、大幅な節税効果が期待できます。
STEP3:税額の計算
最後に、STEP2で算出した課税譲渡所得に所有期間に応じた税率を掛けて、最終的な納税額を算出します。
税額=課税譲渡所得×税率
不動産を売却した年の1月1日時点での所有期間によって、税率は以下のように大きく異なります。
- 長期譲渡所得(所有期間が5年超):20.315%
- 短期譲渡所得(所有期間が5年以下):39.63%
不動産売却時の税金計算のシミュレーション
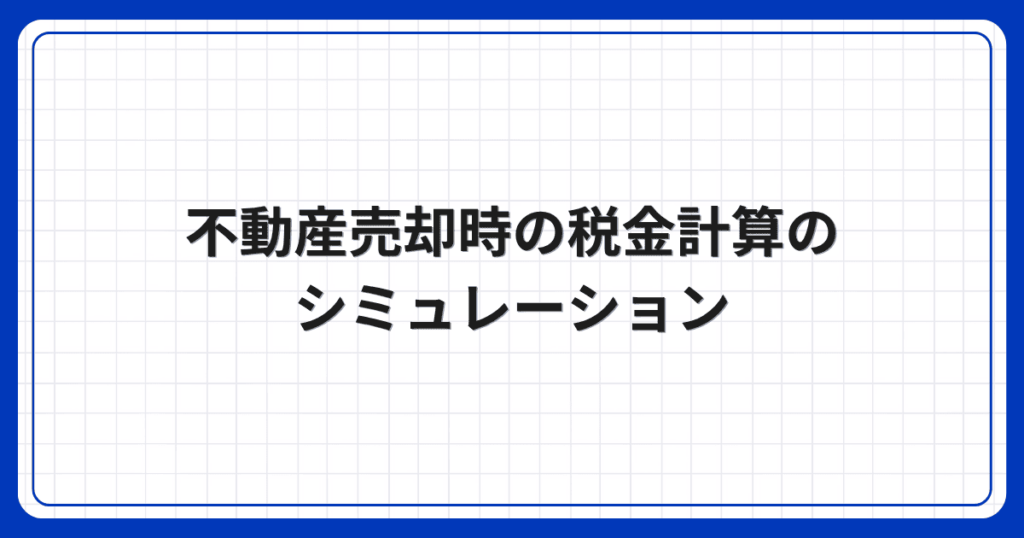
具体的なケースを想定して、税金計算のシミュレーションをしてみましょう。
ここでは「不動産売却時の税金の計算方法」で解説したステップにもとづき計算します。
なお、実際の税額計算では、他の所得や控除なども考慮する必要があります。また、減価償却費の金額は建物の構造や築年数によって変動するため、以下はあくまで概算の例として参考にしてください。
マイホームを10年所有して売却したケース(3,000万円特別控除を適用)
- 売却価格:6,000万円
- 取得費:4,000万円
- 譲渡費用:200万円
- 所有期間:10年(長期譲渡所得)
STEP1:譲渡所得の計算
6,000万円-(4,000万円+200万円)=1,800万円
STEP2:課税譲渡所得の計算
1,800万円(譲渡所得)-3,000万円(特別控除)=0円
※譲渡所得が特別控除額を下回るため、課税譲渡所得は0円
STEP3:税額の計算
0円×20.315%=0円
このケースでは、3,000万円特別控除の適用により、不動産売却による税金はかからないという結果になりました。
投資用マンションを8年所有して売却したケース
- 売却価格:3,000万円
- 取得費:2,500万円(うち建物価格1,500万円)
- 購入時の諸費用:150万円
- 8年間の減価償却費の合計:400万円
- 譲渡費用:100万円
- 所有期間:8年(長期譲渡所得)
STEP1:譲渡所得の計算
まず、売却時の取得費を計算します。
(購入時価格2,500万円+購入時諸費用150万円)-減価償却費400万円=2,250万円
次に、譲渡所得を計算しましょう。
売却価格3,000万円-取得費2,250万円-譲渡費用100万円=650万円
STEP2:課税譲渡所得の計算
投資用物件で特別控除は使えないため、課税譲渡所得は650万円
STEP3:税額の計算
650万円×20.315%=132万475円
このケースでは、約132万円の税金が発生します。
投資用マンションを4年所有して売却したケース
「投資用マンションを8年所有して売却したケース」で、所有期間だけが4年だった場合をシミュレーションします。所有期間が短くなるため、減価償却費の合計額も少なくなります。
- 売却価格:3,000万円
- 取得費:2,500万円(うち建物価格1,500万円)
- 購入時の諸費用:150万円
- 4年間の減価償却費の合計:200万円(8年所有時の半分と仮定)
- 譲渡費用:100万円
- 所有期間:4年(短期譲渡所得)
STEP1:譲渡所得の計算
売却時の取得費を計算しましょう。
(購入時価格2,500万円+購入時諸費用150万円)-減価償却費200万円=2,450万円
次に、譲渡所得を計算します。
売却価格3,000万円-取得費2,450万円-譲渡費用100万円=450万円
STEP2:課税譲渡所得の計算
投資用物件で特別控除は使えないため、課税譲渡所得は450万円
STEP3:税額の計算
450万円×39.63%=178万3,350円
このシミュレーションでは、約178万円の税金がかかる結果になりました。所有期間が5年以下だと税率がほぼ倍になるため、長期譲渡の場合と比較して、利益に対する税金の負担が非常に重くなることが分かります。
ここまで、ケース別に税額のシミュレーションを紹介しましたが、複雑な計算が必要な不動産売却では、信頼できる専門家のサポートが不可欠です。
「プロパリー」なら、税務に詳しい優秀な不動産のプロと出会えるので、正確な税額計算と最適な売却戦略を同時に手に入れることが可能です。
不動産売却における特例・特別控除
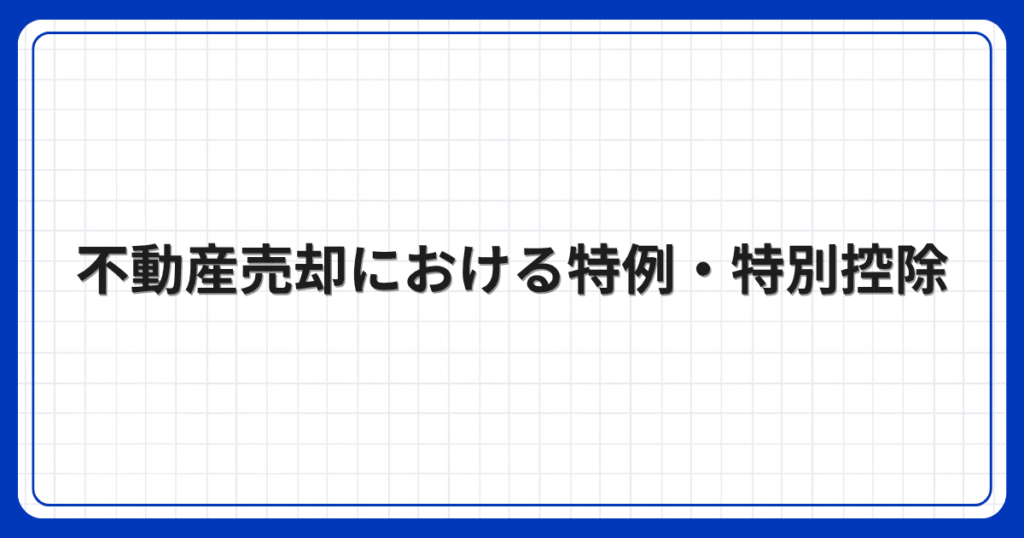
不動産売却では、税負担を大幅に軽減できる特例・特別控除がいくつか用意されています。これらを活用すると手残りが大きく変わるため、必ず自分が該当するか確認しましょう。
3,000万円特別控除
マイホーム(居住用財産)を売却して得た利益から、最高3,000万円までを控除できる特例です。この特例を適用するためには、主に以下の条件を満たす必要があります。
- 売却する不動産が自分の居住用であること
- 住まなくなってから3年を経過する日の属する年の年末(12月31日)までに売却すること
- 売却した年の前年、前々年にこの特別控除や他の特例を使っていないこと
- 売主と買主が、親子や夫婦といった特別な関係でないこと
10年超所有軽減税率の特例
マイホームの所有期間が10年を超えている場合、課税譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について、税率がさらに低くなる特例です。3,000万円特別控除と併用が可能で、通常の長期譲渡所得の税率である20.315%よりも有利な、14.21%の軽減税率が適用されます。
不動産売却で節税するためのコツ
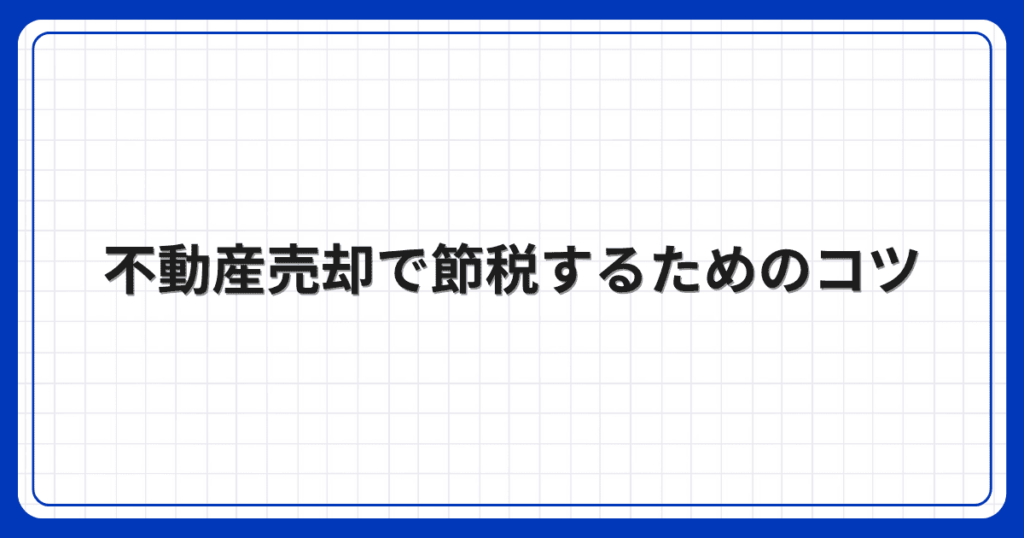
不動産売却にかかる税金を、合法的に少しでも減らすためのコツを解説します。
3,000万円特別控除が使える間に売却する
マイホームの売却では、3,000万円特別控除の適用条件を満たしている間に売却することが、もっとも効果的な節税方法です。住まなくなってから3年以内という期限があるため、賃貸に出すなどの活用を検討している場合でも、期限内の売却を検討しましょう。
また、3,000万円特別控除は3年に一度しか使えないため、複数の不動産を所有している場合は、売却タイミングの調整が重要です。
所有期間が5年を超えるまで待つ
所有期間が5年以下の短期譲渡所得(39.63%)と、5年超の長期譲渡所得(20.315%)では税率が大きく異なります。売却を急がない場合は、所有期間が5年を超えるまで待つことで大幅な節税が可能です。
ただし、不動産価格の下落リスクや維持費用も考慮して判断する必要があります。
取得費・譲渡費用を漏れなく計上する
譲渡所得を圧縮するためには、取得費と譲渡費用をできるだけ多く、そして漏れなく計上することが重要です。
不動産購入時の契約書や仲介手数料、登記・リフォーム費用といった、あらゆる領収書や明細書を大切に保管しておき、経費として認められるものをすべて洗い出しましょう。もし購入時の契約書を紛失した場合は、売却価格の5%を概算取得費として計上できます。
不動産売却後の確定申告のやり方・手順
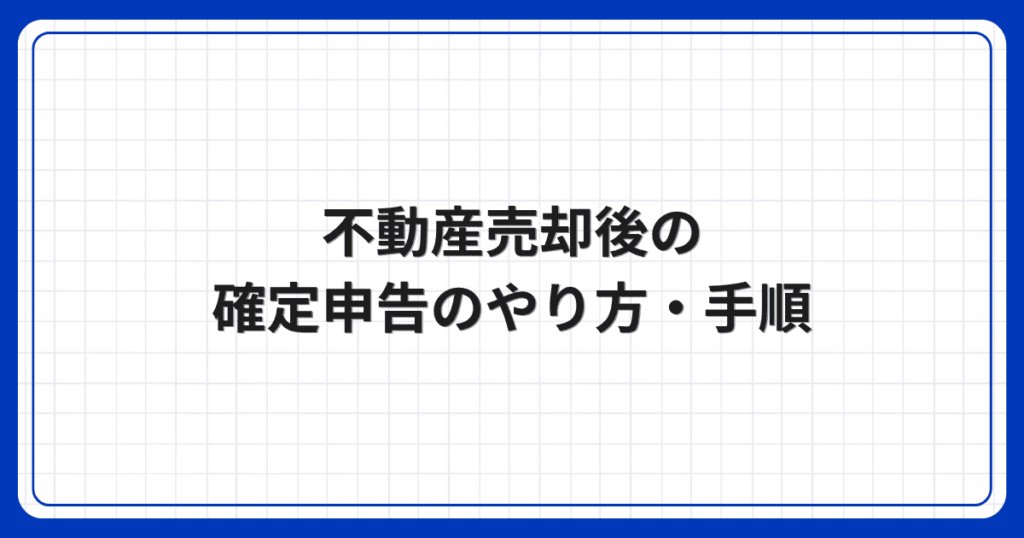
不動産売却で利益が出たり、特例の適用を受けたりする際は、売却した翌年に確定申告が必要です。確定申告の流れを確認しましょう。
STEP1:必要書類を揃える
まず、申告に必要な書類を揃えます。不動産売買契約書や、仲介手数料などの領収書、登記事項証明書といった書類が必要です。直前になって慌てないよう、計画的に準備を進めましょう。
必要書類の詳細については、こちらの記事を参考にしてください。
不動産売却後に確定申告が必要・不要なケース|自分でやる方法や必要書類も解説
STEP2:譲渡所得を計算する
揃えた書類をもとに、売却価格と取得費、譲渡費用を計算し、譲渡所得を算出します。
STEP3:申告書を作成する
国税庁のWebサイトにある確定申告書等作成コーナーを利用するのが便利です。画面の案内に従って入力するだけで、税額が自動計算され、申告書が完成します。
STEP4:税務署に提出する
不動産を売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に、税務署に申告書を提出します。期限内に正しく申告することで、特例の適用を受けられます。
不動産売却の税金に関するよくある質問
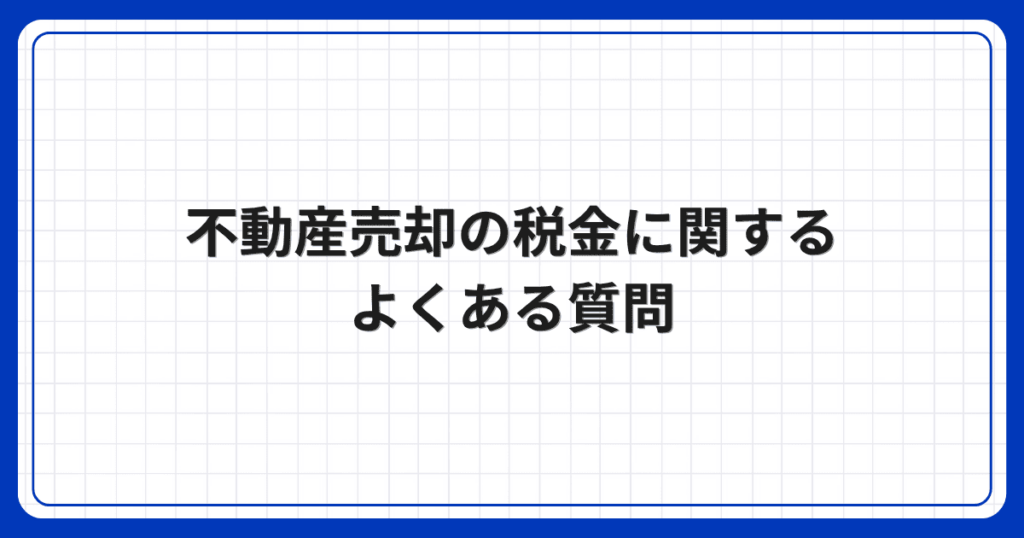
不動産売却の税金に関するよくある質問について回答します。
- 不動産売却の税金はいつ払うことになる?
-
譲渡所得税のうち、所得税の納付期限は、確定申告の期限と同じく原則として不動産を売却した翌年の3月15日です。一方で、住民税は確定申告の情報をもとに市区町村が税額を計算し、翌年の6月頃に納税通知書が送られてきます。
所得税と住民税で支払いの時期が異なることを覚えておきましょう。
- 不動産売却に消費税はかかる?
-
個人がマイホームや投資用物件を売却する場合、その取引に消費税はかかりません。消費税の課税対象は、事業者が事業として行う取引に限られるためです。
ただし、法人が事業として不動産を売却する場合、建物部分の売却代金には消費税が課税されます。また、仲介手数料などの諸費用には消費税がかかります。
- 不動産の贈与を受けた人は税金を支払う必要がある?
-
不動産を贈与で取得した場合、もらった人は贈与税を支払う必要があります。贈与税には年間110万円の基礎控除があり、不動産の評価額が基礎控除額を超える場合に課税されます。
相続時精算課税制度や住宅取得等資金の贈与の特例といった軽減措置もあるため、不動産の贈与を受ける際は、事前に税理士などに相談すると安心です。
不動産売却の税金を少しでも減らしたいならプロパリー
引用元:プロパリー
| 価格 | 無料 |
| 対応OS | iOS/Android |
| 4つの強み | プロを比較して選べる 将来の収支予測 リアルタイム収支管理 買主から直で売却オファー |
不動産売却の税金は、売却価格と譲渡費用に大きく左右されます。つまり、少しでも高く、そして無駄な費用をかけずに売却してくれる、優秀な不動産会社をパートナーに選ぶことが、最大の節税対策になるのです。
不動産売却で税金の負担を少しでも抑えたい人におすすめなのが、利用者と不動産のプロをマッチングさせるサービス「プロパリー」です。
特徴的なのは、その公平さにあります。プロパリー自身が物件を売買していないため、特定の会社や物件に偏った提案をされる心配がなく、常に投資家や売主の立場に立ったサポートを受けることが可能です。
プロパリーをダウンロードして物件情報を登録すると、実績豊富な複数の不動産投資のプロからオファーが届きます。
利用者は届いたオファーの内容を比較検討し、もっとも信頼できる専門家を選ぶだけなので、初めての不動産売却でも安心して進められるのが魅力です。
プロパリーは無料で利用可能です。納得できる不動産売却を頼りになる味方と進めたい人は、この機会にプロパリーをダウンロードしましょう。
まとめ:節税して不動産売却の利益をアップさせよう
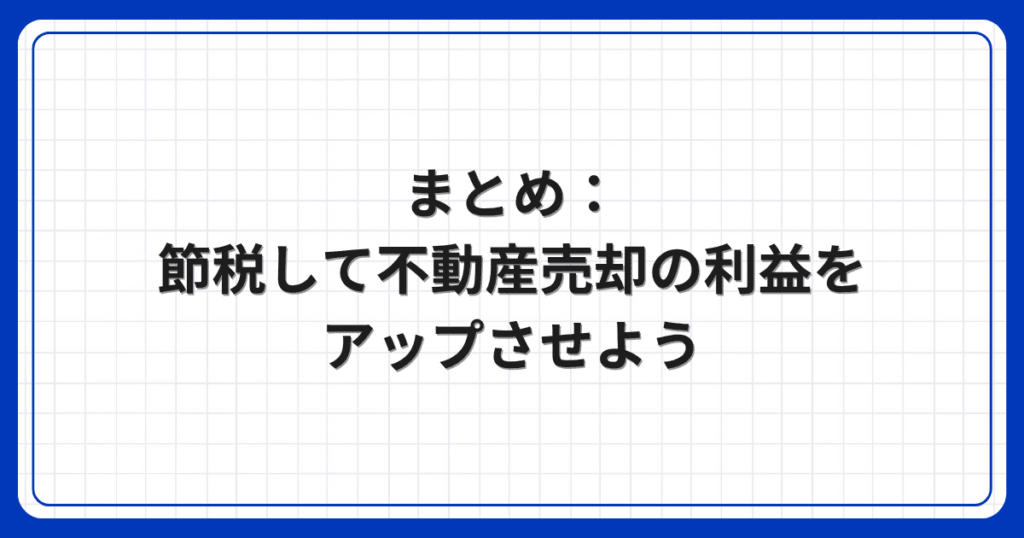
不動産売却における譲渡所得税の仕組みは複雑です。しかし、以下の3つの基本を押さえておけば、大枠を理解できます。
- 利益に対して課税される
- 所有期間が5年を超えるかが重要
- 特例を使えば大幅に節税できる
もっとも重要なのは、不明な点は税務署や税理士などの専門家に相談し、正しい知識をもって手続きを進めることです。そして、その前段階である売却そのものを成功に導くため、信頼できるプロ探しは決して妥協してはいけません。
ぜひプロパリーを活用して、資産価値を最大化してくれる最高のプロを見つけ、手残りを最大化する不動産売却を実現してください。














